図解でわかる!~ネック反り編~
みなさま、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか
大型連休を楽しまれている方、お仕事を頑張られている方、ちょっと一息吐きませんか?
さて、今回は「ネックの反り」について解説です。
ネックの反り、ギターやベースを調整に出すと必ずと言って良いほど耳にする言葉ですよね。「反ってますねー」「順反りですねー」なんて言われても「いまいちピンと来ない…」、「反りってどこを指しているの?」
質問したくても、なんとなく訊きづらい。訊いてみたけれど、なんだかよくわからない。そんな「ネックの反り」について図を絡めながら解説してみたいと思います。
ちなみにネックの各部位はこちらの記事で紹介しています。ご参考下さいませ。
図解スタートです

△…弦の支点 水色線…弦 橙色の長方形…指板(ネック) 赤線…ガイドライン
写真やイラストでは、ごちゃごちゃするので図形を使用し簡略化してみました。手近に楽器をお持ちの方は、ぜひご自身の楽器とこの記事を見比べてみてくださいね。
今回は初心者でも実感としてわかりやすい、弦を基準としたネック反りのチェック方法を紹介します。
まずは準備!使用時のチューニングに合わせましょう。また、新品弦と消耗し劣化した弦では、ネックに掛かる負荷の程度が異なるので、弦はなるべく新しいものを使用しましょう。
お手持ちであればカポと、トラスロッドが搭載されている楽器であれば、ロッドを動かすためのレンチを用意して頂けると、ご自身で反り具合の調整もお試し頂けますよ。
支度は整いましたか?早速、開始です!
試してみよう
!実践のポイント!
楽器のコンディションと演奏のしやすさは当然ながら個人差があるので、理想値以外を悪いと考えるのではなく、あくまで参考程度に捉えてくださいね。

① 演奏する時の要領で楽器を構え、1フレットとジョイントフレット(※1)を同時に押さえます。1フレットの押弦はカポを使用しても良いです。
※1:ジョイントフレットとはボディとネックの継ぎ目位置上にくるフレットを指します。よくわからない場合は下記を参考に押さえてください
エレキギター/ベース:14~17フレットのいずれか
アコースティック/クラシック:12~14フレットのいずれか
② 押弦している2点の距離的な中間に当たるフレットの頂点と、弦の底面(フレットと接する側)に隙間はありますか?この隙間の有無でざっくりとした反りの方向がわかります。
目視でわかりづらい場合は弦をフレット位置の上から軽くタップし、弦に振動を感じられるかで判断してみましょう。ペシペシとフレットに当たった振動を感じる場合、隙間があります。
弦をタップしても弦の揺れを感じない場合は隙間が無い状態です。
③A 弦とフレットの頂点が接しておらず隙間がある場合
この場合は程度に差はあれど、ネックは順反り傾向にあると言えます。
隙間の最大幅が葉書1枚入る位かそれ以下の隙間があり、押弦している両端に向かって狭まっていく状態が、理想的なネックのコンディションと言えます。
隙間の最大幅が明らかに広い場合、順反りが目立つ状態と言えます。
③B 弦とフレットの頂点が接していて隙間が無い場合
この場合、ネックは逆反り、もしくは真っ直ぐな状態です。ここで気を付けて頂きたいのはネックが「逆反り」と「真っ直ぐ」の2つの可能性が存在している、と言うところです。
一見、弦とフレットの頂点に隙間が無いので、ネックが真っ直ぐになってる、と思いがちですが、定規など直線のものを宛がうと実は逆反り、という状況が非常に多いです。
以上がざっくりとしたネック反りの判別方法です。お手元の楽器はどちらに当てはまりましたか?
ネックが順反りしている場合と逆反りしている場合、演奏にはどのような影響があるのでしょうか。この場に書くのはあくまで一例ですが、知っておくと後々、自身で調整を行う場合や修理依頼を行う際に便利ですよ。
ネックが順反りしていると…

順反りしている楽器についてはチューニングを合わせた状態で弦を張ったままにしていると、順反りが進行するリスクが高いです。
特に後者の図(ベースにありがちな順反りの例)に表記しているような順反りの仕方をしているものの中にはハイ起きと呼ばれる症状を併発している場合があり、トラスロッドによる調整では症状が改善できない場合もあります。
使われているネックの材質や、保管環境により程度は異なりますが、深刻化させないためには使用しない時はチューニングを緩める等の対策が必須です。
ハイ起き症状については図解でわかる!~ネックのハイ起き編~にて詳細解説をしていますので気になる方はこちらをチェック!
ネックが逆反りしていると…

逆反りしている楽器については、トラスロッド以外で改善を試みる場合、弦のゲージを少し太いものに変えてみたり、ペグポストに巻き付ける弦の巻き数を増やすことで、逆反りが軽減することがあります。
また、順反りではタブーですが、逆反りの場合はチューニングを合わせた状態のまま数日程度保管し、反りが動かないか様子を見るのもありです。
ネック反りを調整するには
トラスロッドが搭載されている楽器であれば、ロッドを動かすことで反りの度合いを変えられる事が大半です。
正常に機能しているトラスロッドであれば、ロッドを緩める方向に動かすとネックは順反り方向に動き、ロッドを締める方向に動かすとネックは逆反り方向に動きます。
順反り、逆反りが目立つ状態の楽器に関してはトラスロッドでの調整を試して頂く価値ありです。
ご自身で試される場合、個体に合ったレンチを使用し、無理な力を加えたり、一気にロッドを回す事は絶対に避けてください。楽器の破損や怪我に繋がります。少しずつ、様子を見ながら操作してください。
また、長年使用されていない楽器や古いものだと、ロットが錆などで固着し脆くなっている事があります。この場合、無闇に力を加えるとロットが折れ、ロッドの仕込み直しといった大がかりな修理後必要になりますので、不安要素が少しでもありましたら我々にご相談ください。
トラスロッド調整についてクローズアップしたトラスロッド回しませんか?【リペアマン寺田の「アコギは打楽器!」五打目】の記事もありますので、興味がある方はぜひ、参考にしてみてください。
もちろん、クラシックギターやヴィンテージのトラスロッドが非搭載の楽器であっても何かしらのアプローチを行うことで、反りの度合いを軽減させることができます。
また、ロッドが搭載されていない楽器の場合、押弦・開放共に音に差し支えなければ無理に反りを修正するよりも、症状を進行させないよう調整を行う場合もあります。
個人で試す事が出来る内容としては、弦のゲージを変えるとネックに掛かる負荷の程度が変わり、反りの度合いが多少なり変動します。
弦ゲージの変更のみでは対処しきれない反りが出ていて、演奏のしづらさを感じる、出音に支障がある、といった場合には我々にご相談ください。より良いコンディションになるよう、修理・調整のご提案をさせて頂きます。
中には一筋縄でいかないネック反りもあります。順反りと逆反りが混在していたり、反りの中心がハイポジションに寄っていたり・・・
「ちょっと、どう手を付けて良いかわからない」そんな楽器がありましたら我々、島村楽器のリペアまでご相談下さい!
過去の関連記事はこちら
図解でわかる!シリーズ一覧はこちら
- 図解でわかる!~ネック反り編~
- 図解でわかる!~ナット交換編~
- 図解でわかる!~ネジ取付編~
- 図解でわかる!図解でわかる!~ビビりの原因編~
- 図解でわかる!~「すり合わせ」と「リフレット」 その違い編~
- 図解でわかる!~ネックのハイ起き編~
- 図解でわかる!~パーツの名称・ネック編~
※修理費用は同じ症例でも楽器の種類や形状・仕様によって異なる場合があります。
ご不明な点はお近くの島村楽器にぜひともご相談ください。
♪耳より情報♪
- ☆Twitterはじめました☆
ギター・ベースの修理に興味のある方はぜひ、フォローお願いします!
記事中に表示価格・販売価格、在庫状況が掲載されている場合、その価格・在庫状況は記事更新時点のものとなります。
店頭での価格表記・税表記・在庫状況と異なる場合がございますので、ご注意下さい。














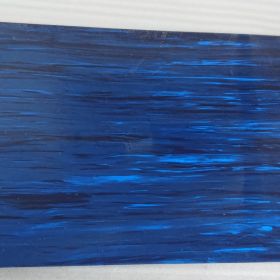





「この楽器の状態って弾きやすいの…?」そんな不安な点を取り除きながらプレイスタイル・楽器に合ったベストコンディションを一緒に探していきましょう!