
代表的なDAWソフトといえば Steinberg(スタインバーグ)社の「Cubase」(キューベース) 。パソコンで作曲や編曲される方に高い支持を得ており、当社でもトップクラスの人気を博しているDTMソフトウエアです。
そんな「Cubase」をこれから購入したい方も多いかと思いますので、初めて導入される方に向けて、どのような製品か、種類や違いなどをまとめていきたいと思います。
目次
–Cubase の種類
—Cubase 無料版について
—Cubase AI と LE の主な機能の違い
—Cubase クロスグレード版とは
—Cubase アカデミック版とは
—Cubase 製品版のグレードの違い
–初心者におすすめなのは?
–インストールが不安、基礎的な使い方を教わりたい
Cubase の種類
「Cubase」は、メインとして3つのグレードがラインナップする有料の製品版(通常版)があり、他に無料版、LE版、AI版があります。また、それ以外にもクロスグレード版、アカデミック版というものもあります。
–Cubase 無料版
–Cubase AI / Cubase LE と製品の違い
それぞれの購入方法は次のとおり。
Cubase 無料版
「Cubase」には無料で試せる体験版(トライアル版)があります。こちらは、 Steinberg のアカウントを作成することで、誰でもダウンロードすることが可能で、「Cubase」の製品版と同じ機能を60日間無償でお試しいただけます。
「Cubase」を買ってもお持ちのパソコンで動作できるか不安という方も一度確認することができます。
-Q:Cubase 体験版で作成したファイルは引き継げますか?
–A:可能です。Cubase 体験版をインストール後に製品版を購入した場合、体験版で作成したプロジェクトは同バージョン、同じグレードであれば読み込むことができます。
-Q:Pro とELEMENTS どちらにするか検討しています。どちらも試せますか?
–A:可能です。それぞれ60日間を体験することができます。ただし、上位グレードをインストールした場合、下位グレードのプラグインを読んでしまう可能性があるため、先に下位グレードを試してからが良さそうです。
ダウンロードする前に ひとまず Cubase の制作の流れが知りたいという方は、下記の動画が参考になるかと思います。
Cubase AI と Cubase LE
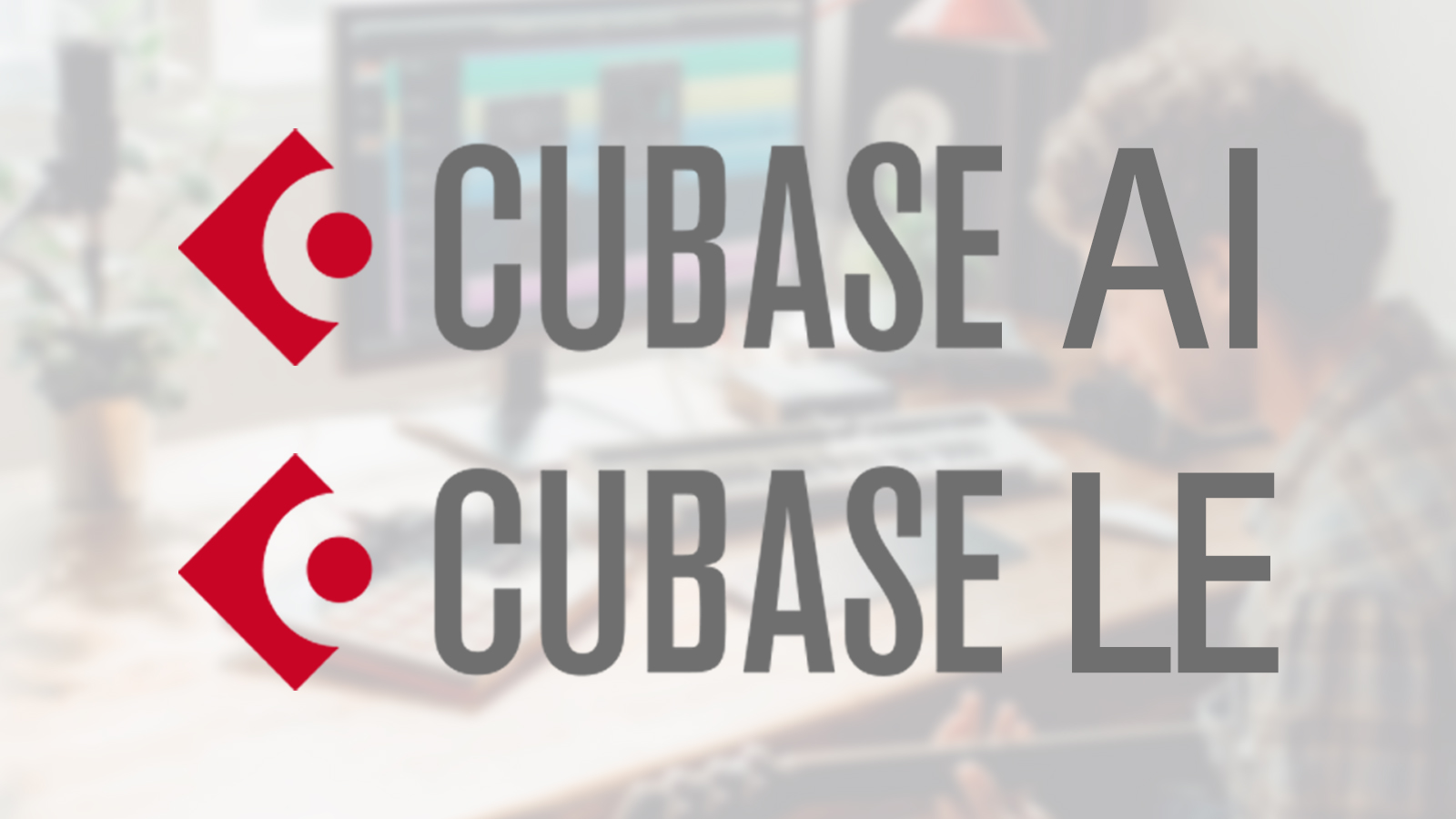
「Cubase AI」と「Cubase LE」は製品版(通常版)の機能を制限したソフトウエアです。上記の体験版とは異なり、使用期限はとくにありません。
「Cubase AI」は、Steinberg やYamaha 製品に付属されており、現行機種(2023年12月現在)での主な製品は下記となります。
| 【オーディオインターフェイス】 | ||
|---|---|---|
| UR12B | UR22C / UR22C Recording Pack / UR24C / UR44C / UR816C | |
| 【デジタル・ミキサー】 | ||
| DM3 シリーズ | ||
| 【ミキサー】 | ||
| MG20XU / MG16XU | MG12XU / MG12XUK / MG10XU / MG10XUF | |
| AG03MK2 / AG06MK2 | AG08 | |
| 【シンセサイザー】 | ||
| MX88 | MX61BK / MX49BK | |
| MONTAGE Mシリーズ | MODX+ シリーズ | |
| 【マイク】 | ||
| AG01 | ||
「Cubase LE」は、Steinberg やyamaha 以外のメーカーの製品に付属されることがあり、購入したい製品のサイトでご確認ください。
Cubase AI と LE の主な機能の違い
「Cubase AI」と「Cubase LE」ですが、どちらもハードウェアに特典として付属されるソフトウエアというのは共通ですが、機能に差があり「Cubase AI」が上位版となります。
各種トラック数の制限数が大きな違いですが、初心者として一番大きな差は、「Cubase LE」はヤマハのサポートが受けられない点です。なのでトラブルなどが起こった場合も自力での解決が必要になります。「Cubase AI」は、簡易サポート対象となっていますので、初心者の最初のハードルであるインストールや初期設定などをヤマハに確認することができます。
機能的な違いですが、どちらもしっかり楽曲制作をするなら機能が限定的なので、あくまで製品版(通常版)を購入する前のお試し的な位置づけかもしれません。
| AI | LE | |
|---|---|---|
| 最大サンプリングレート | 192 kHz | 96 kHz |
| MIDI トラック | 48 | 24 |
| オーディオトラック | 32 | 16 |
| VST インストゥルメントトラック数 | 16 | 8 |
| VST インストゥルメント数 | 2 | 2 |
| インストゥルメントのサウンド数 | 185 以上 | 185 以上 |
| VST オーディオエフェクトプラグイン数 | 28 | 23 |
| インストゥルメントスロット数 | 8 | – |
Cubase クロスグレード版とは

「Cubase」のラインナップには、「Cubase Pro クロスグレード版」があります。クロスグレード版とは対象となる他社製の音楽制作ソフトウェアをお持ちの方が安く購入できる優待版のことです。
下記の対象ソフトを所持していて、「Cubase Pro」をご検討の場合は「購入申込書」にご記入の上「証明書」(ライセンス登録情報やレシートなど)をご持参いただくと店頭で受付可能です。
なお、クロスグレード版を購入後も所持しているソフトはそのままご使用いただけます。
※ Artist および Elements のクロスグレードはありません。
※ 対象はフルリテール版の正規登録ユーザーに限ります。
※ 「購入申込書」が印刷できない場合は店頭でご記入いただけます
クロスグレード対象製品 (2023年12月現在)
-INTERNET Ability Pro
-Ableton Live 8 以降(Standard または Suite)
-Apple Logic 9 以降
-Avid Pro Tools 9 以降 (Pro Tools, Pro Tools HD, Pro Tool Studio, Pro Tools Flex, Pro Tools Ultimate)
-Bitwig Studio 1 以降
-Cakewalk Sonar X2 以降 (Platinum または Professional)
-Cockos Reaper (Commercial license only)
-Imageline FL Studio 11 以降 (Signature または Producer)
-Magix Sequoia 9 以降
-Magix Samplitude Pro X 1 以降
-MOTU Digital Performer 7 以降
-Propellerheads Reason 6 以降
-Presonus Studio One (Professional)
※ Intro / Lite / First / Student / Fruty Edition / Artist / Cakewalk by Bandlab / Prime / Discounted License / Music Studio / Essentials / Elements / LE その他 FreeBundle 版、およびサブスクリプション版は対象外です。
※ Avid 社のサブスクリプション版は対象です。

Cubase アカデミック版とは
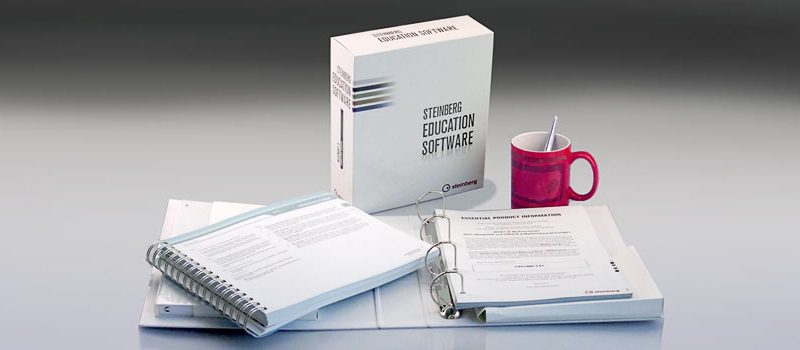
「Cubase」のアカデミック版は対象となる日本国内の教育機関や教職員、学生の方が購入いただける製品です。
アカデミック版と製品版(通常版)の仕様は同じなので機能に差はありません。ただし、製品版は、付属の音色や音素材を組み合わせて作成した楽曲やリズムパターンなどを、営利目的で使用(楽曲を商品として販売することやYouTubeなどの広告収入対象のサービスにアップロードしたり、配信サービスでご利用したり)することはできるのですが、アカデミック版は商用利用が出来ませんのでご注意ください。
※ 製品版(通常版)でも、音色を単音として書き出したファイルや音素材を加工しないままの商用利用はできません。使用者オリジナルの制作が必要です。
ご購入方法は、「購入申込書」にご記入の上、教育機関発行の「身分証明書」をご持参いただくと店頭で受付可能です。対象条件はこちらをご確認ください。また、教育機関(学校)によっては対象外の場合もございます。
※ 「購入申込書」が印刷できない場合は店頭でご記入いただけます。
アカデミック版ラインナップ
アカデミック版は下記の3つが用意されています。
–「Cubase Pro」
–「Cubase Artist」
–「Cubase Elements」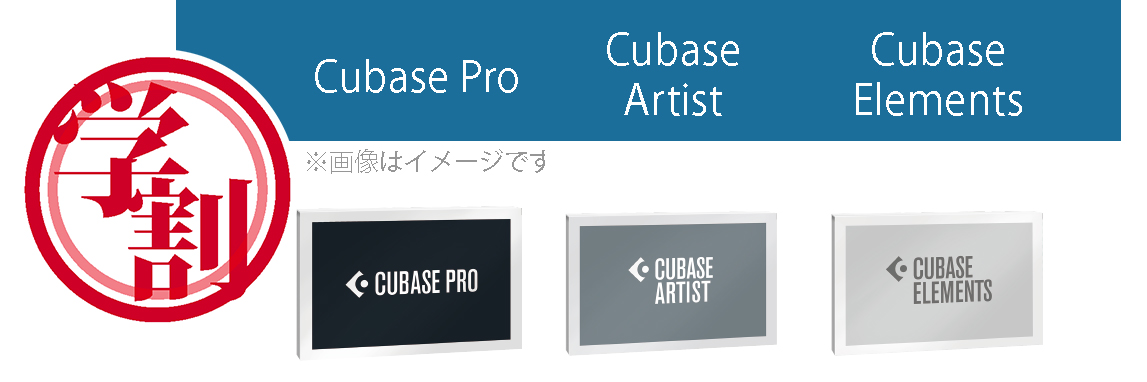
Cubase 製品版

「Cubase」の製品版(通常版)は、作曲家やアーティストに使用されている「Pro」、中間のクラスにあたる「Artist」、最下位版の「Elements」の3つのグレードがラインナップされており、店頭およびオンラインストアで購入することができます。
▼ 主な機能の違い
各グレードの特徴的な機能を抜粋した比較です。細かい比較表は Steinbergサイトをご確認ください。
| PRO | Artist | Elements | |
|---|---|---|---|
| サウンド数 | 3000 以上 | 2600 以上 | 1000 以上 |
| オーディオエフェクト数 | 87 | 62 | 45 |
| MIDI エフェクト数 | 17 | 17 | 0 |
| オーディオワープクォンタイズ | ◯ | ◯ | – |
| テイクコンピング | ◯ | ◯ | – |
| VariAudio 3 | ◯ | ◯ | – |
| オーディオ書き出し | ◯ | 一部 | – |
| EQ / スペクトラル比較 | ◯ | – | – |
| ワークスペース | ◯ | ◯ | – |
| コードアシスタント近接モード | ◯ | – | – |
| テンポ/拍子/移調トラック | ◯ | ◯ | – |
| MPE 対応 | ◯ | ◯ | – |
| テンポ検出パネル | ◯ | – | – |
| インプレイスレンダリング | ◯ | ◯ | – |
| オーディオアライメント | ◯ | – | – |
| MixConsole スナップショット | ◯ | – | – |
| ステレオコンバインパンナー | ◯ | – | – |
| SuperVision | ◯ | ◯ | – |
| SpectraLayers One | ◯ | ◯ | – |
上記は「Cubase」の性能の違いとともに、よく使われている機能をまとめた主な違いになります。そのため、こちら以外でも差がありますのでご注意ください。
それぞれの機能を簡単に説明すると下記のとおり。
- サウンド数
- 付属するソフトウエア音源の音色数
- オーディオエフェクト数
- 付属するエフェクトプラグインの数
- MIDI エフェクト数
- 打ち込みに重宝するツールの数
- オーディオワープクォンタイズ
- オーディオ波形のタイミングを合わせる。録音したデータのリズムを調節したいときに便利
- テイクコンピング
- 複数録音をしたときにベストなテイクを選択するのに便利
- VariAudio 3
- ピッチ補正ツール。ボーカルの音程を正しく修正したり、異なる音程に極端に変化させられる
- オーディオ書き出し
- Proは柔軟な書き出し方法が選択可能。指定の場所や任意のチャンネルのみ書き出す、エフェクトをオフで書き出すなど。また、複数チャンネルをバラバラに書き出すマルチトラックエクスポート対応もProのみ
- EQ / スペクトラル比較
- 2 つのチャンネルの音の周波数成分を可視化して比較しながらEQ調整が可能
- ワークスペース
- 打ち込み用の画面やミックス用の画面など、複数の作業モードを切り替えられるとても便利な機能
- コードアシスタント近接モード
- コードを提案を提案してくれる機能。Pro は提案コードを中心に、合わせやすいコードから難しいコードまでを分かりやすく表示可能
- テンポ/拍子/移調トラック
- 楽曲のテンポや拍子を変更できるトラックを作成可能
- MPE 対応
- 多彩な表現を演奏できるMPEに対応。
- テンポ検出パネル
- オーディオまたは MIDI パートのテンポを分析して、プロジェクトのテンポに合わせたり、各トラックを分析したテンポに追従させたりが可能
- インプレイスレンダリング
- MIDIデータを瞬時にオーディオに変換する機能。CPUの節約にも重宝する
- オーディオアライメント
- 指定したオーディオを別のオーディオのタイミングを合わせる機能。ハモリをメインボーカルのタイミングに合わせたり、ダブルトラックの作成に便利
- MixConsole スナップショット
- MixConsole の設定(エフェクトや各パラメーター)を保存し、呼び出せる機能
- ステレオコンバインパンナー
- ステレオトラックのステレオ幅を調節することが可能
- SuperVision
- メーターリングプラグイン。レベル、スペクトラム、位相などのメーターを表示することが可能
- SpectraLayers One
- 波形を視覚的に編集することが可能。ボーカルを抜き出すまたはボーカル除去することが可能
初心者におすすめなのは?

「作曲&編曲家を目指す」「楽曲を販売したい」「音楽で食べていきたい」とプロ志向の方であれば「Cubase Pro」で決まりです。「趣味で楽しみたい」という方も「Cubase Pro」あるいは「Cubase Artist」でしょうか。
一般的にどんな製品でも「高いもの=多機能」なイメージがあるかと思います。そのため、「ほとんど使わない機能だったら嫌だな・・」とか「多機能なほど難しそう・・」って思ってしまいますよね。
DAWソフトも同じく高いほど多機能ではありますが、高いものには操作を簡単にするツールが搭載されています。と言うよりも上記の比較の通り、上位製品にしか入っていないことも多いのです。変な言い方をすれば最上位製品は(便利ではないツールも)すべて入っているので機能が多い=多機能となりますが、下位製品は便利ではないツールで制作することになります。なので乱暴にいえば初心者に向いているのは上位製品といえます。
DAWソフトは、音楽制作において中核となるもので、長く使用するものです。もし、予算が難しい場合はDAWソフトはケチらず、ほかの周辺機器、たとえばスピーカーやオーディオインターフェースを最初は低価格に抑えるのも選択肢に入れるべきです。もし、どうしても予算がホントに難しい場合はハードウェアに付いているCubase AIをおすすめします。
なので、おすすめ順位としては下記になります。
+「Cubase Pro」
+「Cubase Artist」
+「Cubase AI」付きハードウェア
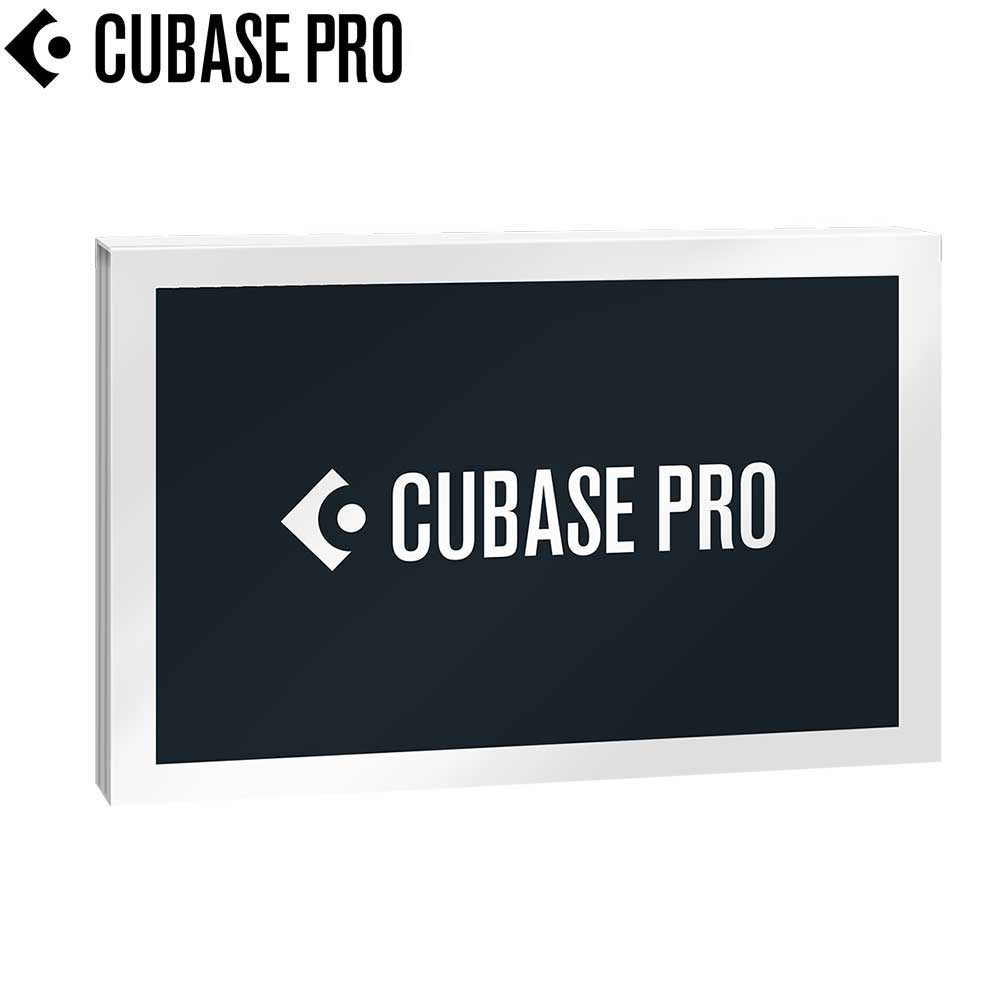
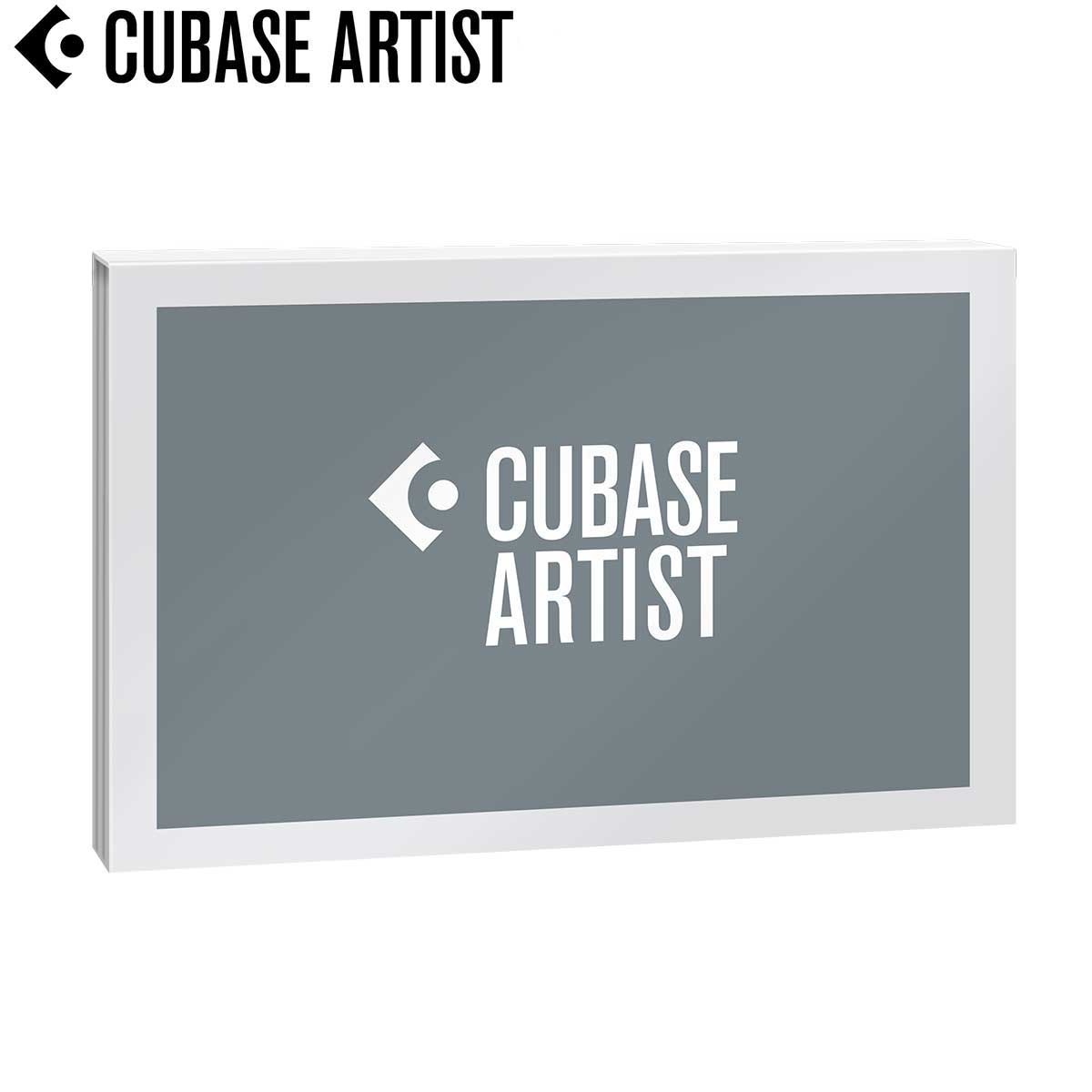
インストールが不安、基礎的な使い方を教わりたい
どのDAWソフトウエアを導入したとしても最初の関門はインストールと初期セットアップです。「インストールが上手くいかない」「音が出ない」「鍵盤が反応しない」といった声はソフトウェアは非常に多いのです。
国内正規品を購入した場合は、メーカーへ問い合わせることができますが、コンピューターの問題はソフトウェア以外で原因があることも多く、なかなか原因を突き止めることが困難なこともあります。
島村楽器では、パソコンが不得意な方でもDTMを始められるように「DTM安心サポート」のサービスを実施しています。
このサービスでは、お客さまのパソコンをお預かりしソフトウェアおよび周辺機器の設定を代行いたします。
ぜひ、導入前に合わせてチェックしてみてください。
▼ 「DTM安心サポート」の詳細はこちら
DTM安心サポートと使い方サポート




