
代表的なDAWソフトである Avid Technology (アビッド・テクノロジー) 社の「ProTools」(プロツールス) 。プロフェッショナルのレコーディング・スタジオで業界標準となっており、楽器録音や作曲される方など個人使用でも高い支持を得ているDTMソフトウエアです。
そんな「Pro Tools」ですが、無料版や有料の製品版(通常版)、クロスグレード版やアカデミック版など以外にも、買い切りでもある永続ライセンス版、月や年ごとに利用できるサブスクリプション版、また、それらを更新する製品などとても複雑かつラインナップが多く、ProTools のどれを買えば良いのかわからない方も多くいらっしゃいます。
そこで、どのような製品をラインナップしているか、種類や違いなどをまとめていきたいと思います。
Pro Tools とは?

レコーディングスタジオに行った事のある方なら必ず知っているのがProTools です。音楽制作スタジオ、映画関連や放送局、プリプロダクション等では業界標準と言われています。
プロ用・業務向けのイメージのプロツールスですが、エンジニアを目指している方、バンドやシンガーソングライターにも定評があります。
とくに、楽器や歌など録音を軸に作曲される方に人気で、DTMとして個人使用されている方も多くいらっしゃいます。また、メインのDAWと分けて使用されている方もいて、レコーディングスタジオで録音をする際にファイルを持ち込むときや宅録してからミックスエンジニアに渡すとき、仕上がったデータをもらって自分でも編集したいときなどに使用されているようです。
Pro Toolsは、レコーディング、編集やミックスが行えるDAWソフトで、録音やミックスなどオーディオを扱うことに特に優れているのが特徴です。MIDI対応はもちろんソフトシンセも付属しているのでオーディオ録音以外のパートを打ち込みすることも可能です。ただし、音源などプラグインを追加したい場合、AAXという独自の規格を採用しているため注意が必要です。
Pro Tools 無料版
「ProTools」の無料版は「Pro Tools Intro」と体験版(トライアル版)があります。
Pro Tools Intro

「Pro Tools Intro」はAVIDのアカウントを作成することで誰でも入手可能で、使用日数の期限はなく永続して使用できます。
しかし、無料ということもあり多くの機能制限があります。また、便利なツールやサポートがなく使いにくさはあるので実際の製品版 Pro Tools の確認には向いていません。Pro Tools がどんなのかざっくりでも見てみたい、楽器のオーディオ録音やリズムパートの打ち込みを体験してみたい、という方に向いているかと思います。
Pro Tools Intro 主な機能制限
-オーディオトラック8トラックのみ使用可能
-インストゥルメントトラック8トラックのみ使用可能
-MIDIトラック8トラックのみ使用可能
-同時イン / アウト数4chのみ
-同梱プラグイン/ツールがIntro Plugin(36種)のみ
-Pro Tools Inner Cirle なし
-Pro Tools | Sonic Drop なし
-Melodyne Essential 別売り
-ユーザーサポートなし
また、下記URLのAVIDサイトでPro Tools Intro に含まれているソフトウェア、プラグイン、バーチャル・インストゥルメント、サウンドを確認できます。
「Pro Tools Intro」に含まれるプラグインやシンセ
なお、「Pro Tools Intro」から製品版に乗り換えたい場合、「Pro Tools Intro」で作成したセッションファイルはそのまま引き継ぐことができます。
Pro Tools Trial
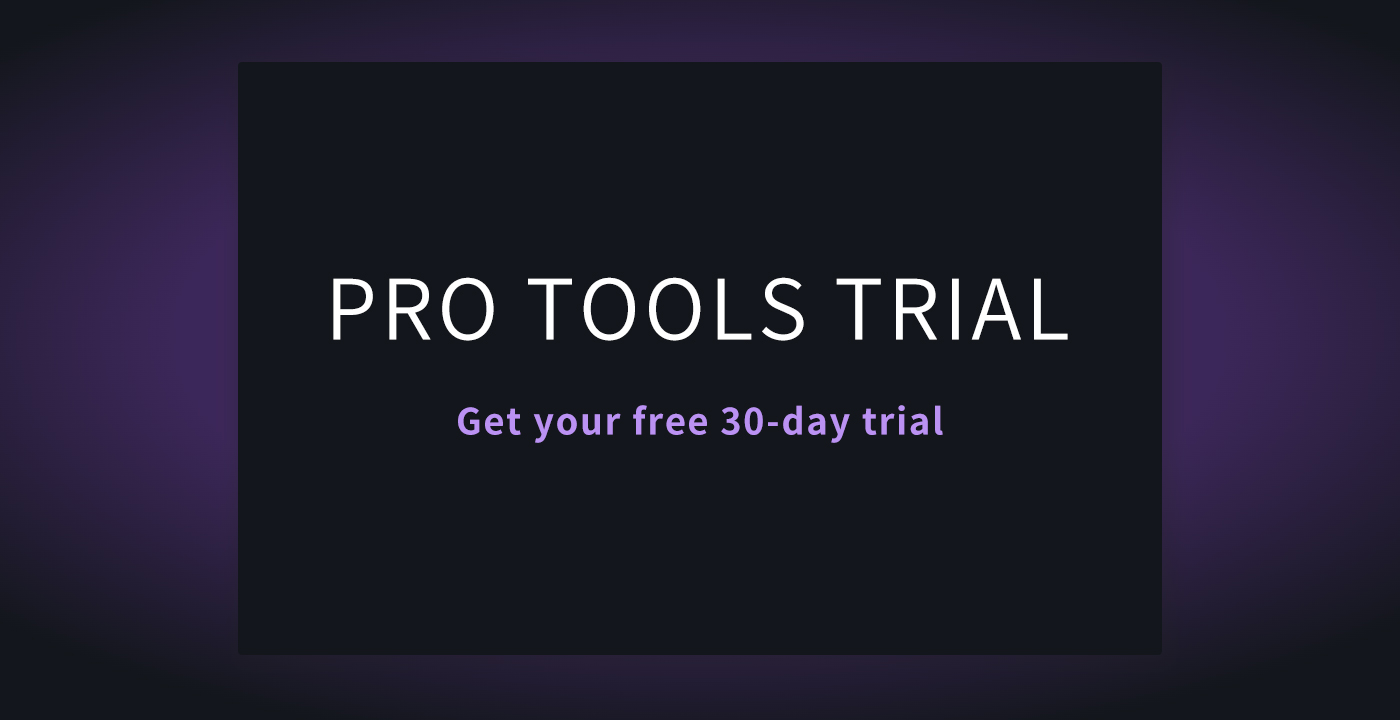
Pro Tools の体験版(トライアル版)はAVIDのアカウントを作成することで誰でも入手可能で、使用日数は、30日間のみ「Pro Tools Ultimate」として使用が可能です。30日を過ぎると「Pro Tools Intro」へ移行されます。
製品版である「ProTools」を買っても、お持ちのパソコンで動作できるか不安という方、実際の製品版 Pro Toolsの仕様を確認したい方はこのトライアル版を体験してみるのが良いと思います。
「Pro Tools Ultimate 体験版」
Pro Tools 製品版

ProToolsの有料製品版(通常版)は、プロスタジオが導入する「Ultimate」中間のクラスにあたる「Studio」最下位版の「Artist」があります。
通常版とは、購入するのに条件がなく、ProTools をこれから導入したい方がご購入いただける製品となっています。
ProToolsの通常版には、サブスクリプション版と永続版があります。
Pro Tools 製品版のグレードの違い
各グレードの特徴的な機能を抜粋した比較です。細かい比較表は メーカーサイトをご確認ください。
| Pro Tools Artist | Pro Tools Studio | Pro Tools Ultimate | |
| オーディオトラック数 | 32 | 512 | 2048 |
| インストゥルメントトラック数 | 32 | 512 | 512 |
| MIDIトラック数 | 64 | 1024 | 1024 |
| AUXトラック数 | 32 | 128 | 1024 |
| フォルダートラック数 | 32 | 128 | 1024 |
| ビデオトラック数 | – | 1 | 64 |
| VCAトラック数 | – | 128 | 128 |
| マスタートラック数 | 1 | 64 | 512 |
| イン / アウト 数 | 16 | 64 | 最大256 ※1 |
| オーディオチャンネル | ステレオのみ | ステレオ サラウンド Dolby Atmos Ambisonics | ステレオ サラウンド Dolby Atmos Ambisonics |
| 対応AVIDハードウェア | MBOX Studio | MBOX Studio, Pro Tools | Carbon, Pro Tools | Carbon Pre, VENUE | S6L | MBOX Studio, Pro Tools | Carbon, Pro Tools | Carbon Pre, Pro Tools | HDX + interfaces, VENUE | S6L |
| 同梱プラグイン | ARTIST BUNDLE (100種以上) | COMPLETE BUNDLE | COMPLETE BUNDLE |
| ARA 2 Melodyne対応 | 対応(同梱) | 対応(同梱) | 対応(同梱) |
| Advanced automation | 非対応 | 対応 | 対応 |
| サポート | STANDARD | STANDARD | EXPERTPLUS |
※1:256 (Core Audio, ASIO), 192 (HDX Hybrid Engine, HDX Classic), 64 (natively via Thunderbolt)
サブスクリプション版と永続版との違い

サブスクリプション版は有効期限がある一時的なライセンスが提供される製品です。期限が過ぎると使用できなくなるため、引き続き使用する場合は期限内に更新版を購入する必要があります。
永続ライセンス版は、使用期限のない製品のことでいわゆる買い切り版です。一度購入すれば所持バージョンがコンピューターで動作する限り期限なくずっと使い続けられます。
サブスクリプション版は初期費用を少なく始められ、また、いつでも最新のバージョンとInner Circle&Sonic Drop コンテンツ特典が利用できます。永続版は最新バージョンでなければ長く使うほど金額的には安く済み、もし最新バージョンにしたい場合やサポート・プランおよびInner Circle&Sonic Drop コンテンツ特典を利用したい場合は更新することもできます。
どちらも一長一短ありますので、お客さまのご利用環境に合わせて ProToolsをお選びいただけます。
Pro Tools サブスクリプション版

当社でご購入いただけるサブスクリプション版は、「Pro Tools Artist」「Pro Tools Studio」「Pro Tools Ultimate」の年間更新型プランになります。1年ごとに更新をする必要がありますが、常に最新の機能で ProTools がご使用になれます。なお、自動更新(自動請求)ではないため、延長して使用するには更新用の製品が必要です。



Pro Tools 永続ライセンス版

当社でご購入いただける永続ライセンス版は、「Pro Tools Artist」「Pro Tools Studio」「Pro Tools Ultimate」になります。登録時から1年間はサブスクリプション版と同じ、常に最新のProToolsが使用でき、Inner Circle&Sonic Drop(Studio以上)も1年受けられます。ご購入から2年目以降はアップデートが終了し、期間内に一番最後にアップデートが行われた段階のバージョンで永続的に使用できる製品になります。
もしも、無償アップデート期間が過ぎた後、最新バージョンに永続ライセンスを更新したい場合はこちら
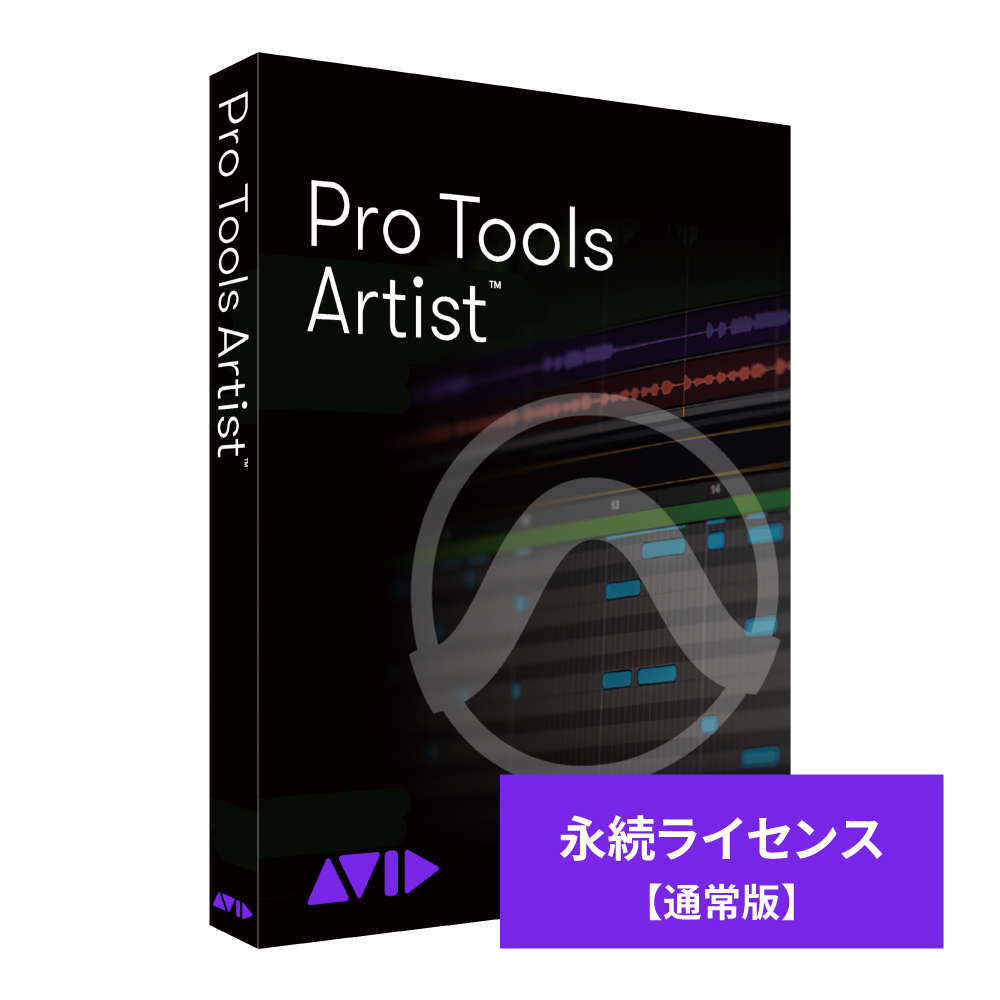
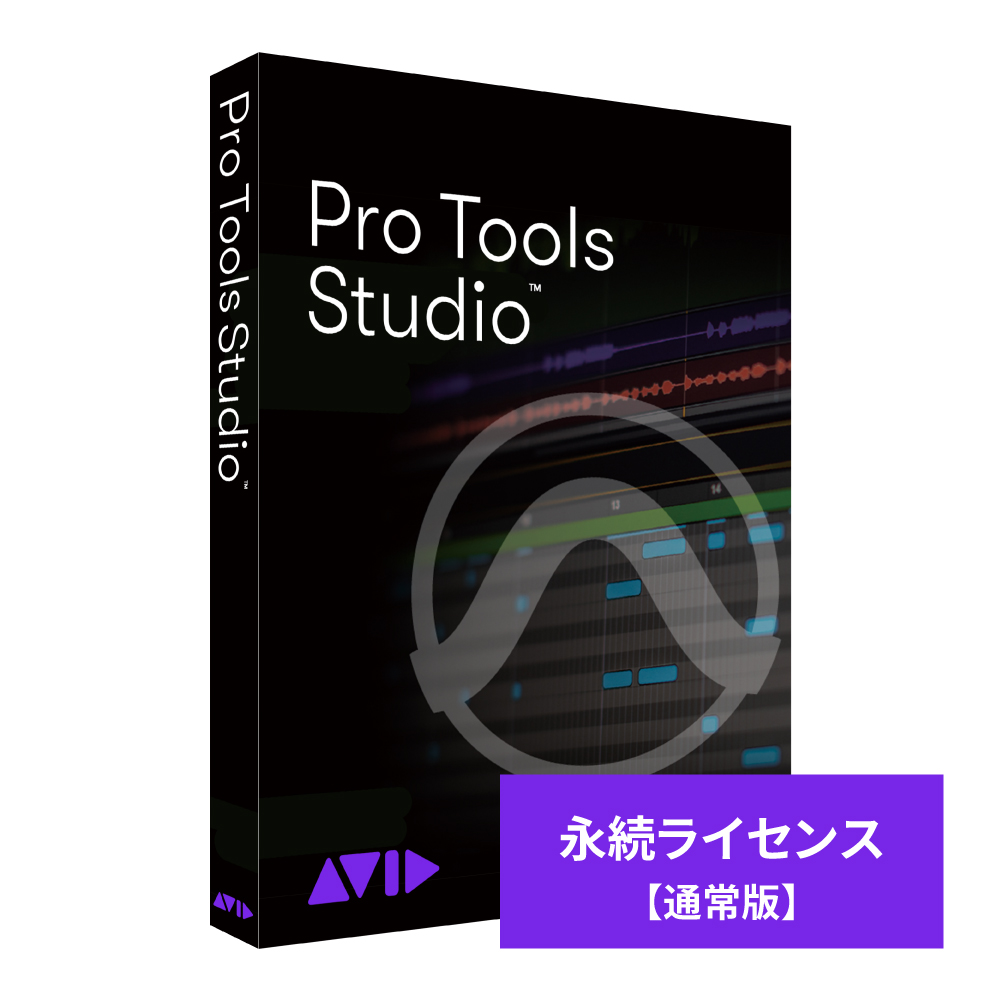
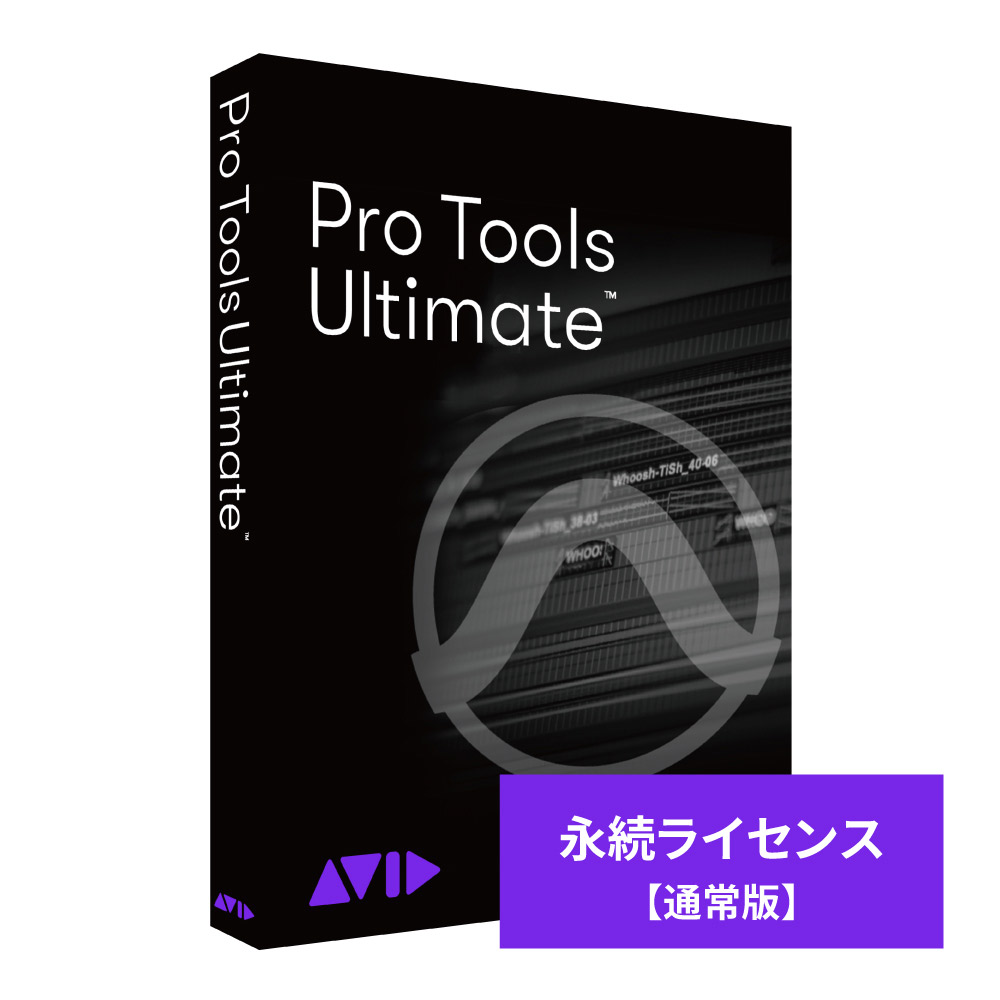
Pro Tools クロスグレード

クロスグレード版とは対象となる他社製の音楽制作ソフトウェアをお持ちの方が安く購入できる優待版のことです。「Pro Tools クロスグレード版」は、AVIDのキャンペーン期間のみで発売されています。通常の製品ラインナップにはありません。
通常版と製品の違いはなく、価格が通常版よりも安く設定されている場合がほとんどですので、他社のDAWソフトをご使用されている方でプロツールスも一緒に使用したい方は大変お買い得です。
キャンペーンは不定期に開催されていますが、期間中は通常版と同じく店頭などで販売されています。
なお対象製品は決まっておりません。その都度、キャンペーン時に対象商品が決まります。
制約事項は、キャンペーンによって変更することもありますが、過去のキャンペーン事情を確認してみると、AVIDが提示した対象DAW製品をお客様自身が所持しているかの確認があります。
Pro Tools アカデミック版とは

「ProTools」のアカデミック版は、対象となる日本国内の教育機関や教育機関に勤務している教職員、学生の方がご購入いただける製品です。
アカデミック版は通常版の仕様と同じなので機能に差はありません。
ご購入方法は、通常版と同じように店頭でアカデミック版をお申し込みいただけます。価格は、学割価格となります。
ご購入後、資格証明書類1通をご用意の上、メーカーサイトで認証の手続きが必要になります。アカデミック版の購入資格、条件および確認については、ご購入前にかならず下記URLよりご確認ください。
プロツールスのアカデミック版の購入資格と条件
当社でご購入いただけるアカデミック版は、「Pro Tools Studio」「Pro Tools Ultimate」のサブスクリプション版です。資格要件・条件を満たす学生および教職員の方がご購入いただけます。
※教育機関用は各店舗までお問い合わせください。


Pro Tools 更新版とは

Pro Tools 更新版とはすでにPro Toolsをお持ちの方を対象にPro Toolsを更新するための製品です。
Pro Tools 更新版は、ProToolsの有料製品版(通常版・アカデミック版・クロスグレード版)の永続ライセンス版あるいはサブスクリプション版をご使用の方、またはご使用されていた方がご購入いただける製品です。
Pro Tools サブスクリプション 更新

当社でご購入いただけるサブスクリプションの更新は、「Pro Tools Artist」「Pro Tools Studio」(通常版/アカデミック版)「Pro Tools Ultimate」(通常版/アカデミック版)の年間更新型プランになります。
サブスクリプション版を現在ご使用していて使用期限を延長したい場合、こちらでさらに1年間追加してご使用いただくことが可能です。
※サブスクリプションの使用期限が過ぎた場合は更新できません。再度、Pro Tools サブスクリプション版あるいはPro Tools アカデミック版をご検討ください。
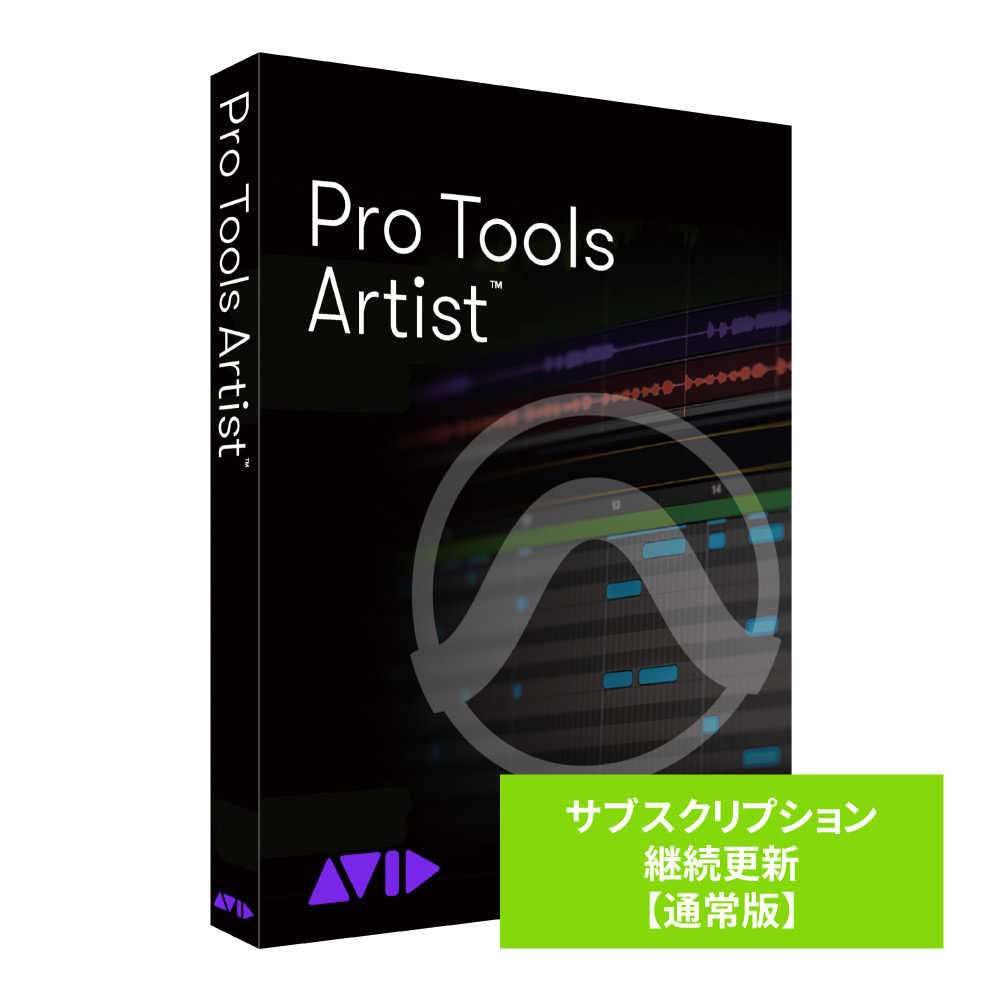

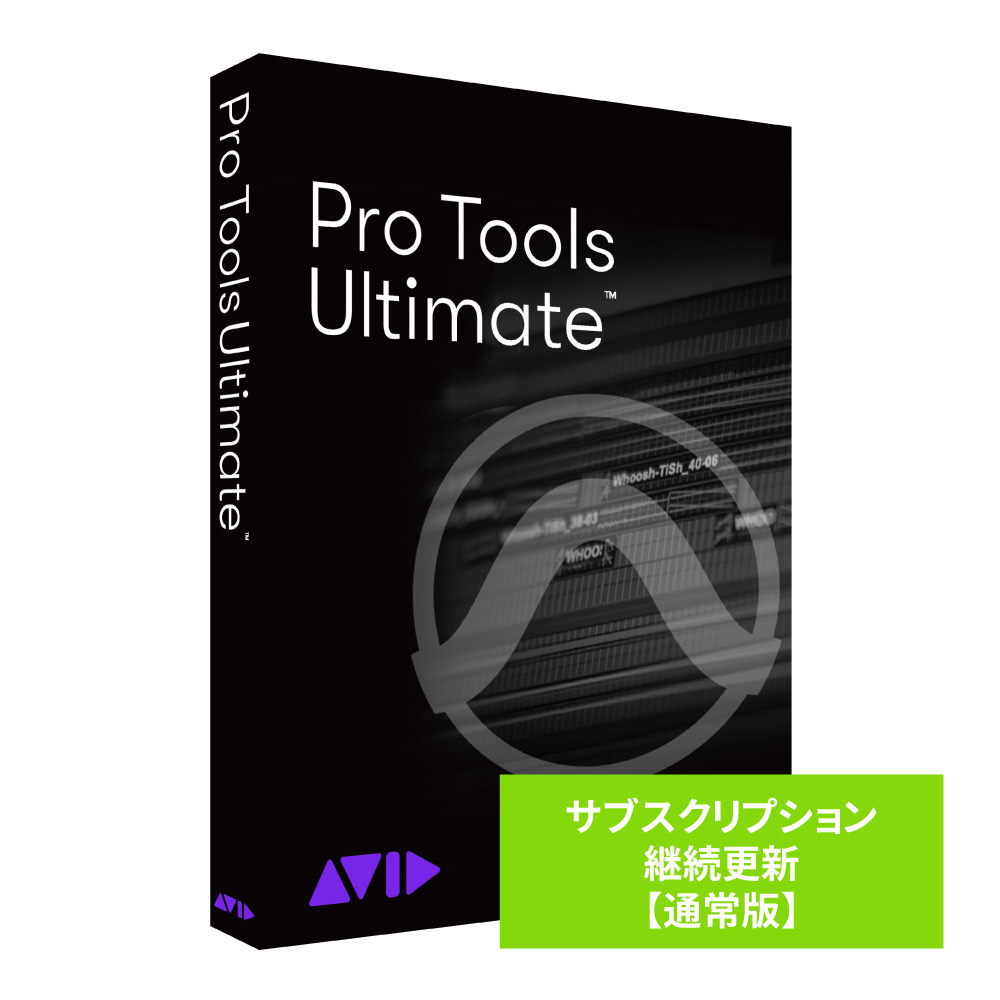
▼下記はサブスクリプション・アカデミック版の更新用
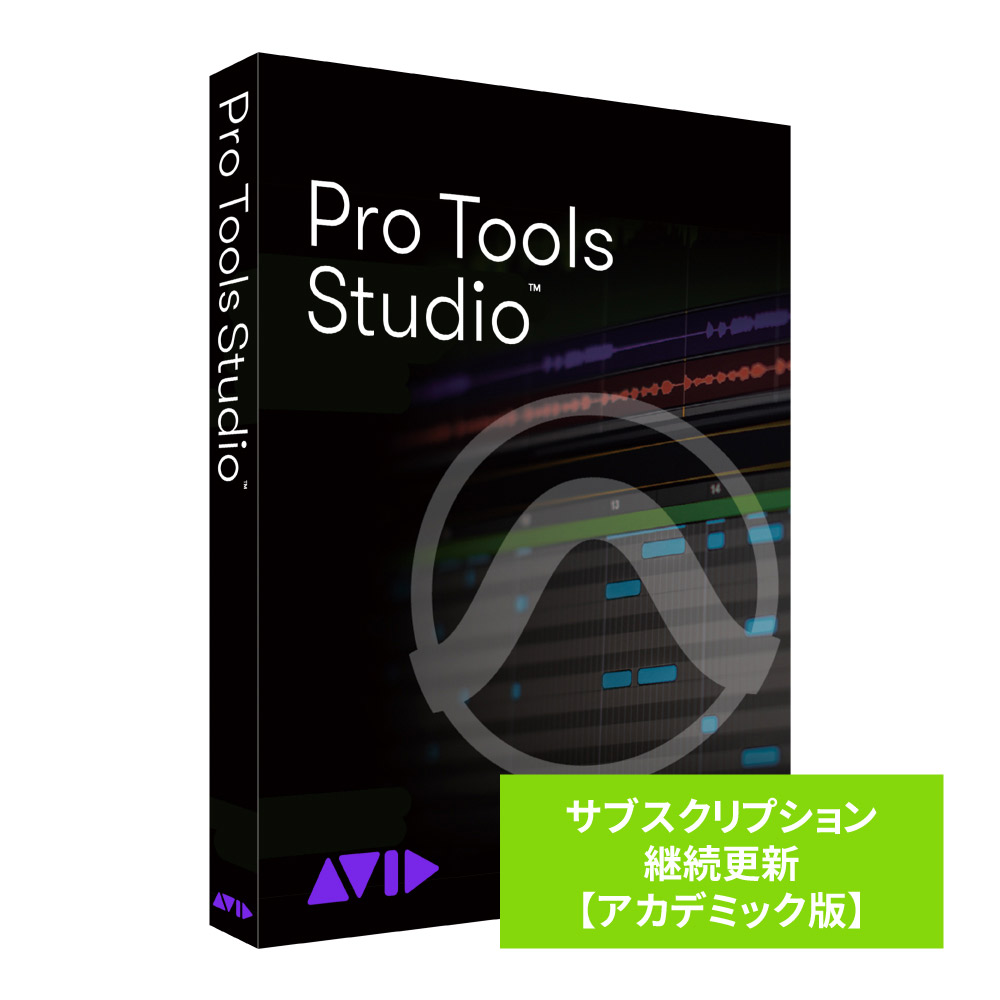

Pro Tools 永続ライセンス 更新

永続版の購入後、1年が経ち、2年が経ち、そんな中アップデートによって欲しい新機能が出てきた場合、諦めることはありません。更新版のご購入で製品登録後、追加で1年のアップデート期間を手に入れられます。
当社でご購入いただける永続ライセンスの更新は、「Pro Tools Artist」「Pro Tools Studio」(通常版/アカデミック版)「Pro Tools Ultimate」になります。
※アップデート期間は、1年のアップデートの権利が切れてしまった方は登録日から1年、アップデート権利を持っている方は権利期間の残り日数 +1年のアップデートが手に入ります。
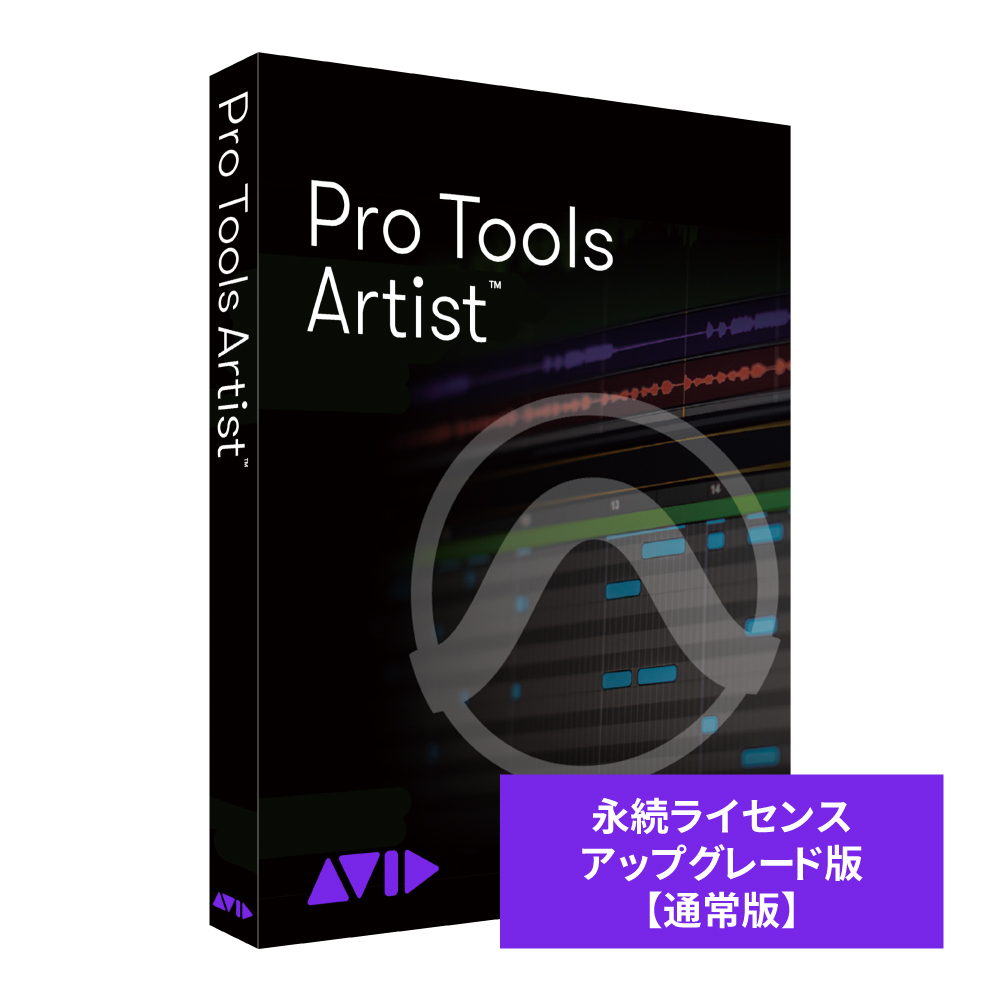
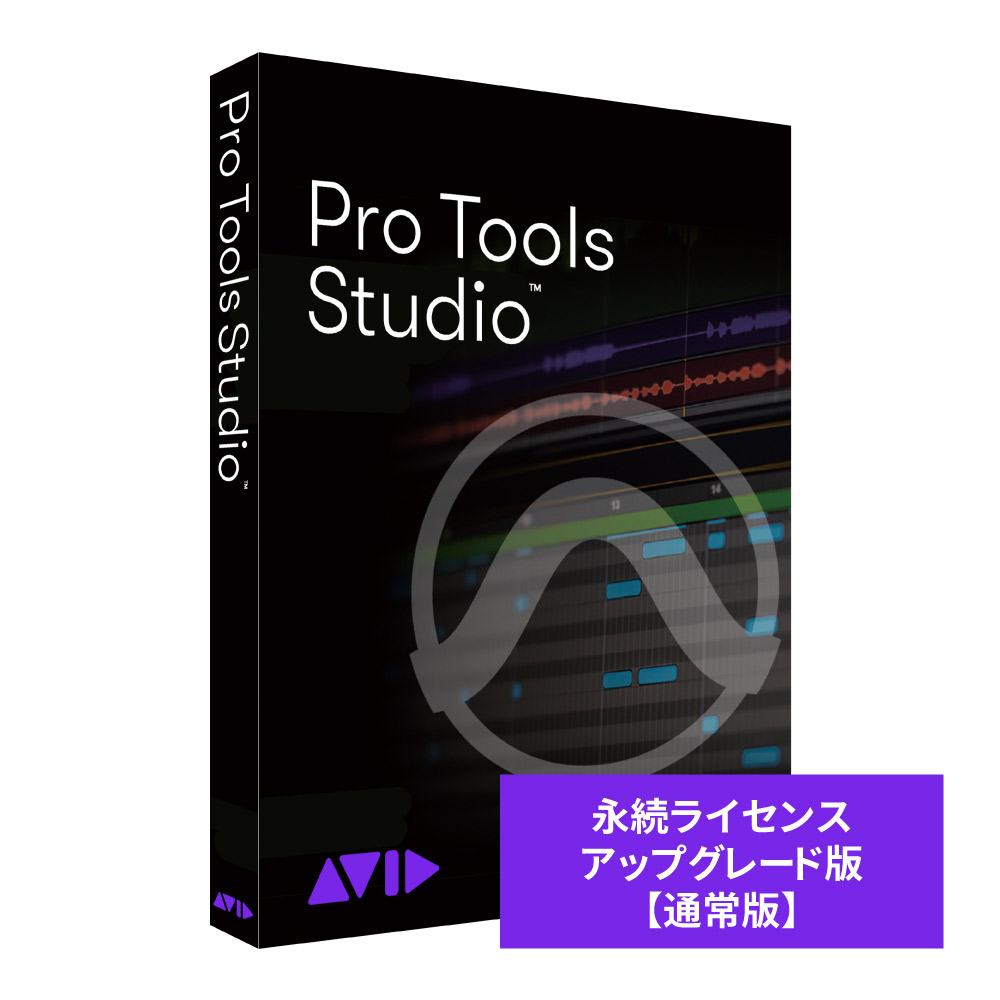
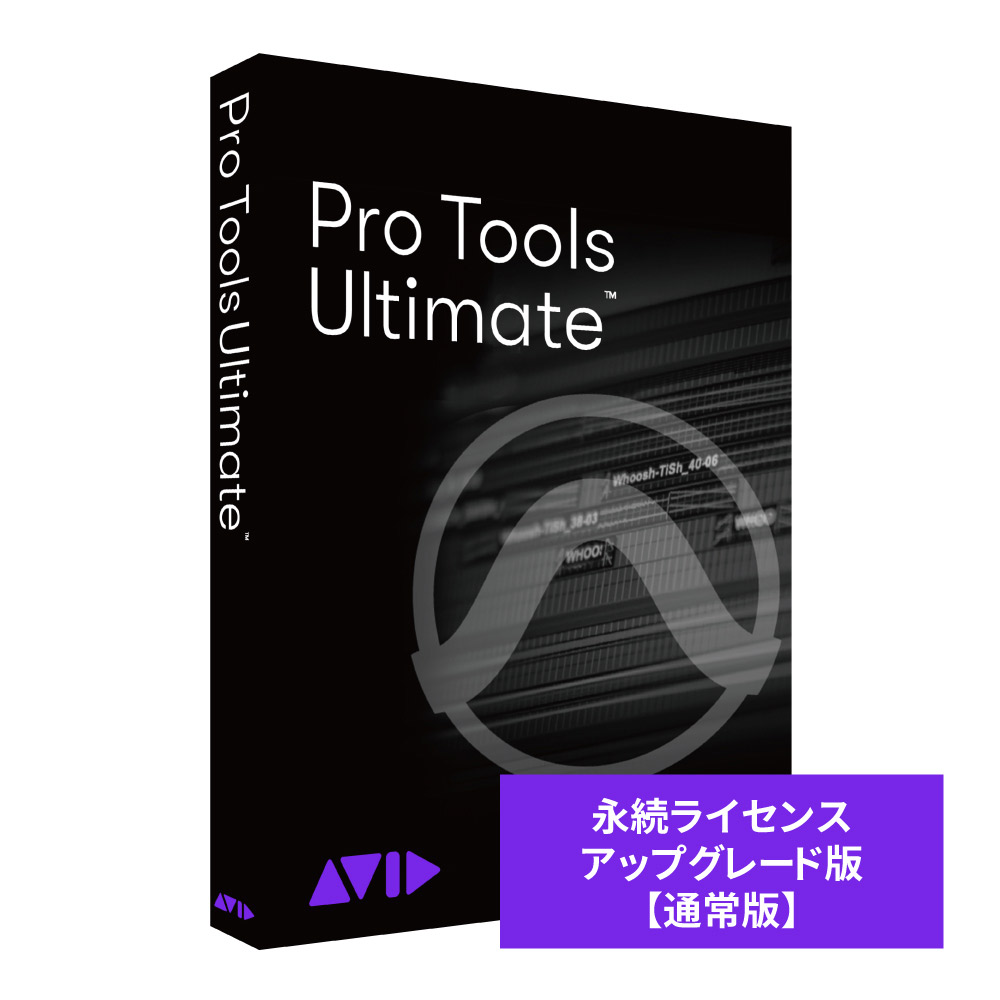
▼下記は永続ライセンス・アカデミック版の更新用

Pro Tools サポートプランとは
ProToolsの有料製品版(通常版)には、サポート・プランが期間限定で付属します。
Standard SupportにつきましてはPro Tools 有償版に通常付与されているサポートプランです。このプランにはAVIDマスターアカウント上での問い合わせケースの作成、対象期間中のアップグレード権が含まれております。
Expert Support Planにつきましてはポストプロダクション向けのサポートプランになっており、上記に加えて電話サポートや案件に対しての優先順位が大きく変わります。
各種サポートプランの内容については以下をご確認ください。
各種サポートプランの内容
初心者におすすめなのは?
DAWソフトは、音楽制作において中核となるもので、音楽が日常になり楽しむほど長く使用するものです。これは音楽を趣味で楽しむにも本格的にプロの作曲家を目指すあるいは配信など不特定多数の方に楽曲を披露したい方にも当てはまります。
なので、DAWソフトを選ぶ基準として、基本的に推奨しているのは、一番高いスペックをもつ製品です。
Pro Tools Ultimate と Pro Tools Studio の違い

しかし、DAWソフトの中でPro Toolsは毛色が異なります。Pro Toolsで最上位製品は「Pro Tools Ultimate」ですが、こちらを初心者が自宅で使用するにはほとんどの場合オーバースペックになってしまいます。というのも下位版である「Pro Tools Studio」でも初心者に十分な機能があるからです。
とはいえ、シャトルモードやスクラブトリムツールなどの再生機能、TrackPunchやDestructivePunch、レコードロックなどの録音機能、クリップ自動フェードイン/アウトやクリップ置換機能など、「Pro Tools Ultimate」にしかない作曲や録音で便利な機能もあるので絶対オススメできないという訳でもありません。
「Pro Tools Ultimate」を個人使用でオススメする方は、フィルムスコアリングなど映像作品を制作される方、ライブコンサートなど高度なフィールド録音を目指す方、オーケストラなど大規模な収録が必要な方、9.1chなどのイマーシブサラウンドの制作やHDXシステムを導入する方、あとは予算に問題ない方でしょうか。
Pro Tools Studioと Pro Tools Artist の違い

中堅クラスの「Pro Tools Studio」でも、音楽制作においてプロクオリティ作品を作るのに遜色ありません。なので、初心者の方が迷うのは「Pro Tools Studio」と「Pro Tools Artist」かと思われます。
「Pro Tools Studio」では、サラウンドやDolby Atmosなどのマルチチャンネルが扱えます。最近では音楽ストリーミングサービスで気軽に空間オーディオを聴くことができるので身近になりました。ただ、初心者にとって最初から制作するには難しいので、別の視点で違いを見ていきます。
Pro Tools Studio は動画が扱える
ビデオトラックの機能は Artist には無く Studio にあります。
movやmp4などのビデオファイルを読み込み、映像を確認しながら曲を作成したり、効果音をつけることが可能なので、音入れのタイミングが容易になり作業効率が上がります。
また、対応するビデオのオーディオを抽出することも可能なので、録画した音声を修正することも可能です。
映像に音楽をつけるのは今や日常的です。YouTube などの動画作成、ホームビデオのBGM作成などを考えている場合は、ビデオトラック機能があったほうが良いでしょう。
Pro Tools Studio はVCAトラックを搭載
VCAトラックの機能があるのも「Pro Tools Studio」 の特徴です。VCAとは、複数の信号を同時に制御できるコントローラーのことで、簡単に言えば、複数トラックのボリュームなどをまとめて操作できるリモコン的なトラックです。
例えば、VCAトラックで歌と伴奏に分けて、伴奏だけの音量を動かすといったことができる訳です。使い方的にはドラム、ギターなどオケの各パートをVCAトラックにまとめ、それぞれの各パートの音量操作をしやすくします。
便利かつ効率化するオートメーション機能
オートメーション機能は Artist にもありますが、その操作性には大きく差があり、Studioはオートメーションをより細かく設定することも可能です。
例えば、クリップのゲイン設定をトラックのボリュームオートメーションに変換したり統合させたり、録音したオートメーションを前のオートメーションに自動的に変更するAutoMatchなど他にも高度なことが行えます。
クリップエフェクトと「HEAT」
クリップエフェクトや「HEAT」が搭載されているのも「Pro Tools Studio」からになります。クリップエフェクトはクリップ(リージョンとも言われるトラック内のオーディオデータ)にエフェクトを割り当てる機能で、非破壊でEQ、フィルタ、ダイナミクスを処理できます。
「HEAT」はアナログテイストを加える機能です。ビンテージのアナログ・コンソールのハーモニックカラーレーションやサチュレーション、アナログ・テープの音の特性をセッションのオーディオ全体に適用することができます。
他にも「Pro Tools Studio」にしか無い機能がたくさん
他にも「Pro Tools Artist」にはない特徴としては、タイムラインの柔軟な再生および編集やプラグインなどのインサート遅延表示などのメーター設定および表示、オートメーションの後のレベル調整に便利なトリムモード、複数ソースを同時に書き出すマルチバウンス(最大10チャンネル、最大24ソース)、ステムデータの配信用など複数ステムを別々ファイルあるいはインターリーブされた1つのファイルにバウンスすることも可能。
録音スタジオなどで収録した「Pro Tools Ultimate」セッションデータを開く場合、超過するトラックや搭載していないトラックがなくなりますが、「Pro Tools Studio」の方が制限が低い分、連携しやすいメリットもあります。
「Pro Tools | MBOX」※サブスクリプション版のPro Tools Studio 付属
Pro Tools 導入におすすめするグレード
ここまで、それぞれのグレードの違いをお伝えしましたが、結局、どれがおすすめかと結論するならば「Pro Tools Studio」をおすすめします。
「Pro Tools Ultimate」は少し高度すぎる、「Pro Tools Artist」は機能制限が意外とある、よって「Pro Tools Studio」であれば、万能でずっと使い続けられるのでは無いでしょうか。
ただ、少なめのトラック数でしか活動しない用途、例えば、ピアノやアコースティックギターの弾き語りのみ収録したい、ポッドキャストの編集をしたいなどであれば「Pro Tools Artist」で十分かも知れません。
なので、おすすめ順位としては下記になります。
+「Pro Tools Studio」
+「Pro Tools Artist」
+「Pro Tools Intro」
インストールが不安、初期設定をしてほしい
どのDAWソフトウエアを導入したとしても最初の関門はインストールと初期セットアップです。「インストールが上手くいかない」「音が出ない」「鍵盤が反応しない」といった声はソフトウェアは非常に多いのです。
国内正規品を購入した場合は、メーカーへ問い合わせることができますが、コンピューターの問題はソフトウェア以外で原因があることも多く、なかなか原因を突き止めることが困難なこともあります。
島村楽器では、パソコンが不得意な方でもDTMを始められるように「DTM安心サポート」のサービスを実施しています。
このサービスでは、お客さまのパソコンをお預かりしソフトウェアおよび周辺機器の設定を代行いたします。
ぜひ、導入前に合わせてチェックしてみてください。
▼ 「DTM安心サポート」の詳細はこちら





–Pro Tools とは?
–Pro Tools 無料版
—Pro Tools Intro
—Pro Tools Trial
–Pro Tools 製品版
—Pro Tools 製品版のグレードの違い
—サブスクリプション版と永続版との違い
–Pro Tools クロスグレード版とは
–Pro Tools アカデミック版とは
–Pro Tools 更新版とは
–Pro Tools サポートプランとは
–初心者におすすめなのは?
—Pro Tools Ultimate と Pro Tools Studio の違い
—Pro Tools Studioと Pro Tools Artist の違い
—Pro Tools 導入におすすめするグレード
–インストールが不安、初期設定をしてほしい