「バンドに憧れて楽器を買ってみたものの、実際に演奏すると難しくてなかなか続かなかった。でも、いつか自分の曲を作ってみたい」そんな経験はありませんか?
とはいえ、『音楽理論も難しそうだし、楽譜なんて暗号にしか見えない』と感じて、自分には無理だとあきらめてしまっている方も多いかもしれません。
しかし、DTMなら、楽譜が読めなくても、楽器が弾けなくても、さらには楽器を持っていなくても、あなたのアイデアやイメージを“曲”というカタチで表現できるのです。
本記事では、「そもそもDTMとは?」から、「どんなことができるの?」「始めるにはどのDTMソフトが必要?」といった疑問まで、初心者にも分かりやすく詳しく解説していきます。
DTMってそもそも何?やさしく解説
DTMとは、“デスクトップ・ミュージック(Desktop Music)”の略で、その名の通り、パソコンを音楽制作システムの「中核」に据え、楽曲を生み出す手法全般を指します。
この言葉が広く認知されるようになったのは、1988年にローランドが発売した音楽制作セット「ミュージくん」が大きなきっかけです。当時は、パソコンからMIDI信号を送り、外部の音源モジュール(ハードウェア)を鳴らして演奏情報を記録する、いわゆる「打ち込み」が制作スタイルの主流でした。
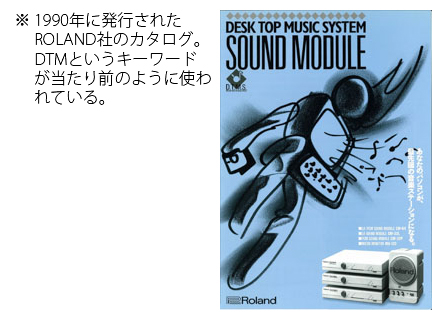
現在、DTMの制作環境はDAW(Digital Audio Workstation)と呼ばれる統合型ソフトウェアが主役です。コンピューターの性能向上に伴い、かつて必須だった音源モジュールの多くは、パソコン内で動作するソフトウェアの音源へと置き換わり、MIDIによる「打ち込み」だけでなく、ボーカルやギターといった生演奏の録音・編集機能も統合されています。
こうした技術の進化やパソコンの高性能化とソフトウェアの低価格化により、音楽制作そのものがより身近なものとなり、プロの音楽家だけでなく、アマチュアや趣味で音楽を楽しむ人々にも広く浸透。DTMは「パソコンを中心とした総合的な音楽制作」そのものを指す言葉として定着しています。
DTMはどんなことができるの?
かつて音楽制作には高価なシンセサイザーやミキサー、レコーダー、防音設備、そして何より熟練のミュージシャンが不可欠でした。ですが今では、そうした機材や環境の多くがパソコン一台とソフトウェアで実現できるようになっています。
DTMの特徴は、大きく4つあります。
1. パソコンが「楽器」になる
ギターやピアノなど本物の楽器を演奏しなくても、パソコン内のソフトウェアが楽器の役割を果たします。音符をマウスやパソコンのキーボードで入力したり、ドラッグ&ドロップでリズムやメロディを作ったりします。
2. 音声の編集、追加を可能にする
マイクを使って自分の歌声やアコースティック楽器を録音し、その音を切り貼りしたりエフェクトをかけたりして編集できます。また、市販のサンプル素材や、著作権フリーの効果音、自分で制作した音などを取り込んで編集、楽曲に自由に追加することができます。
3. 記譜ができなくても楽譜作成・印刷ができる
楽譜を読んだり書いたりできなくても、DTM上で作ったメロディやフレーズは自動的に楽譜として表示・保存できます。オリジナル楽曲の楽譜を印刷して配布して、友達にピアノで弾いてもらったり、バンドで演奏したりすることもできます。
4. 音楽制作のすべてをひとつの場所で
DTMでは「作曲」「アレンジ(編曲)」「レコーディング」「ミックス」など、音楽制作の一連の作業がすべてパソコン内だけで完結します。
たとえば、DTMではこんなことが可能です。
- メロディを打ち込み演奏
- ドラムやベースなど、バンド全体の演奏も一人で再現
- ロックをオーケストラにアレンジ
- 録音した自分の歌や声、楽器の音を曲に合成
- 雰囲気やシチュエーションに合わせた自分好みのBGM制作
- 効果音や環境音なども自由にのせる
まるで、自宅の書斎に自分だけの「アトリエ」を持つようなもの。誰にも邪魔されず、好きな時間に好きなだけ創作に没頭できる…そんな環境をDTMはもたらしてくれます。
楽器経験は必要か?

「でも、やっぱり楽器ができないと曲作りなんて無理じゃ…」
この問いは、DTMに興味を持つ多くの方が抱く疑問かもしれません。
結論からお伝えすると、楽器の演奏経験は、DTMを始める上で「必須」ではありません。
なぜなら、DTMには演奏経験や知識をカバーしてくれる機能をもつソフトウェアが年々増えているからです。
楽譜が読めなくてもOK
ピアノの鍵盤のような画面(ピアノロール)に、マウスで「ド・レ・ミ」と音を置いていくだけでフレーズが作れます。間違えたらすぐに消せるので、納得がいくまで何度でもやり直しができます。
伴奏作りをサポート
楽曲はメロディーだけでなく、さまざまな楽器が合わさって曲になります。そこで和音(コード)の知識だったりするのですが、好きな曲のコード進行を分析してそれを参考できたり、コード進行を自動で提案してくれたりするソフトもあります。
プロの演奏フレーズを呼び出せる
「楽器経験がなく、どうしても演奏者が弾いたようにならない・・」そんなときは、実際にミュージシャンが演奏した膨大なフレーズの中から楽曲に合わせた演奏できるソフトもあります。
リズム作りも、ゲーム感覚で
リズムパターンも、あらかじめ用意されたカッコいいフレーズを貼り付けたり、ゲームのような画面で簡単に入力できる方法もあります。
もちろん、楽器経験や音楽理論の知識があれば、作業がスムーズに進む場面もあります。ですが、それらの知識は、DTMを楽しみながら少しずつ学んでいけば十分です。
それに、経験がないことが「武器」になる可能性があります。
例えば、「ギターはこう弾くべき」「このコード進行が定番」といった”お約束”を知らないからこそ、誰も思いつかないような自由なメロディや斬新なリズムが生まれることだってあります。セオリーにとらわれない発想こそが、あなただけのユニークな音楽を秘めています。
大切なのは「こうでなければならない」と考えることではなく、「こんな音を出してみたい」という好奇心。その気持ちさえあれば、誰にでも創作の扉を開けるのがDTMの魅力です。
DTMソフトの種類

DTMを始めるとき、単に「ソフト」と言っても、その機能や目的によってさまざまなタイプが存在します。ここでは、主なDTMソフトの種類をわかりやすくご紹介します。ただし、これらのほとんどは下記で述べるDAWソフトでできることなので、あくまで参考にしてください。
DAWソフト (音楽制作総合ソフト)
DTMをされている方が最も多く導入していて、制作の中心となるのが「DAW(ディー・エー・ダブリュー)」ソフトです。「ダウ」とも呼ばれます。曲作り、録音、編集、ミックス、仕上げまで、音楽制作に必要なほぼ全ての作業がこれ一つで行えます。
ソフト音源 (バーチャル・インストゥルメント)
ソフト音源は、ピアノやギター、ドラム、シンセサイザー、ストリングス、民族楽器など、さまざまな“仮想楽器”の音をパソコン上で再現するソフトです。DAW上で使える「プラグイン」タイプや、単独動作するアプリケーション型、その両方に対応するものがあります。多くのDAWには基本音源が付属していますが、より多彩な楽器や高品質な音が欲しい場合は、別途追加購入することも可能です。
プラグインエフェクト (エフェクター)
エフェクトプラグインは、リバーブなどの空間系、イコライザーなどのフィルター系、コンプレッサーなどのダイナミクス系、ディストーションなどの歪み系など、音にさまざまな効果や変化を加えるソフトです。主にDAW内で使用され、基本的なものはDAWに付属していますが、より高性能なものや特定用途向けのものを追加購入することもよくあります。
楽譜作成ソフト (譜面ソフト)
主に楽譜を作成・編集・印刷するのに長けたソフトでノーテーションソフトとも言われます。DAWソフトにもこの機能が内蔵されていることもありますが、オーケストラや吹奏楽といった大規模編成の楽譜作成や、複雑な音楽記号の指定、特殊記譜法にも対応でき、より美しく正確なスコアを作成することができます。
マスタリング・波形編集ソフト (オーディオエディタ)
音声編集やノイズ除去、レストア、音質調整、マスタリングなどに特化したソフトです。録音したオーディオデータの微調整や最終仕上げ作業を行う際に活用されます。DAWと連携して使ったり、DAWにプラグインとして追加したりする使い方が一般的です。
ボイス・ボーカル合成ソフト
入力した情報をもとに、デジタルで声を作り出すソフトです。メロディや歌詞を入力してボーカルパート作成する歌声合成ソフト、ナレーションやセリフなどの話し声を生成するテキスト読み上げ(音声合成)ソフトの2種類に大別されます。
サンプラー/ループ素材管理ソフト
さまざまなオーディオフレーズを再生したり、サンプリング素材(サンプルパック)を取り込んで編集したりするソフトです。サンプラーはその音をさらに加工したりすることが可能で、鍵盤などに割り当てて素材から演奏できるようにするものもあります。
コード分析・理論補助ソフト
曲の構造解析や理論的な作曲・演奏支援、コード進行提案を行うソフトです。曲づくり・理論学習を学ぶ作曲初心者だけでなく、プロの作家やアレンジャー、演奏者のアイデア整理や時短にも活用されています。
ビートメイキング・グルーブボックス型ソフト
リズムパターンや繰り返しフレーズの制作に特化したソフト(DAWの一種)です。AKAIのMPCやNIのMASCHINEなどハードウェアと連携して制作することが多いのも特徴です。パターンの打ち込みや素材の組み合わせで素早く曲のベースを構築、リズムやトラック制作を直感的に行えるので、即興演奏もできるのが特徴です。理論ではなく感覚的に作曲できるのがポイントでヒップホップ、EDM、クラブミュージックなどが得意です。
始めるにはどのDTMソフトが必要?

DTMを始めるには、コンピューター、音楽制作ソフト(DTMソフト)、インターフェース、MIDIキーボード、ヘッドホン、モニタースピーカーを揃えるのが一般的です。
そして、その中で必ずパソコンとヘッドホン or スピーカーは必須といえます。
この2つが揃ったら、次はいよいよDTMの心臓部である「ソフトウェア」の導入です。
あなたの目的に合ったDTMソフトを選ぼう
「DTMソフト」には様々な種類があり、どれを選ぶかは「あなたがDTMで何をしたいか」によって変わります。ここでは、目的ごとに最初に導入すべきソフトの種類をご紹介します。
オリジナル曲をゼロから作りたい
→ 最初に必要なソフト:DAWソフト
作曲、編曲、録音、ミックスなど、音楽制作の全工程を一台のパソコンで完結させたい方は「DAWソフト」が必要です。
DAWは、いわば「デジタルの音楽スタジオ」。たくさんの仮想楽器(ソフト音源)やエフェクターがセットになっており、これ一つあれば、ボーカル曲、バンドサウンド、オーケストラ、ゲームのBGMまで、あらゆるジャンルの音楽制作に対応できます。
いわゆる万能型なので、ほとんどのDTMユーザーは、このDAWソフトを制作の中心に置いています。
楽譜の作成や、持っている楽譜の演奏データ化がしたい
→ 最初に必要なソフト:楽譜作成ソフト
「作曲よりも、きれいな楽譜を作って印刷することがメイン」「手持ちの楽譜をパソコンで演奏させて練習したい」という方は、「楽譜作成ソフト)」が最適です。
DAWソフトにも楽譜作成機能はありますが、楽譜作成ソフトは、より専門的で細かな記号の入力や、美しいレイアウト調整に長けています。吹奏楽や合唱のパート譜作成などにも力を発揮します。
この目的の場合、必ずしもDAWソフトは必要ありません。
ボカロPになりたい/自分の代わりに歌ってもらいたい
→ 最初に必要なソフト:DAWソフト + ボイス・ボーカル合成ソフト
初音ミクに代表されるような、キャラクターに歌ってもらう「ボカロ曲」などを作りたい場合、2種類のソフトが必要になります。
- DAWソフト:カラオケ音源(伴奏)を作るために使います。
- ボーカル合成ソフト:メロディと歌詞を入力し、歌声を作るために使います。
ヒップホップやEDMの「ビート」「トラック」を作りたい
→ 最初に必要なソフト:DAWソフト or ビートメイキング・グルーブボックス型ソフト
ヒップホップやクラブミュージックのような、ループやリズムパターンを組み合わせて作る音楽(ビートメイキング/トラックメイキング)がしたい場合、2つの選択肢があります。
一つは、DAWソフトの中でも、特に「Ableton Live」や「FL Studio」といった、このジャンルが得意なものを選ぶ方法。
もう一つは、より直感的かつスピーディーにリズムやフレーズを組み立てることに特化した Serato Studio などの「ビートメイキング・グルーブボックス型ソフト」を導入する方法です。
どちらも、感覚的にトラックを組み立てていく楽しさがあります。
録音した音声のノイズ除去や編集がしたい
→ 最初に必要なソフト:マスタリング・波形編集ソフト
「音楽制作というよりは、録音した音声の編集がメイン」という方もいるでしょう。例えば、「弾き語りの『サー』というような不要なノイズを消したい」「動画コンテンツの会話を聞きやすくしたい」といった目的です。
その場合は、「マスタリング・波形編集ソフト」が最も力を発揮します。DAWでも簡単な編集は可能ですが、ノイズ除去や音質補正といった作業は、専用ソフトの方がより強力かつ簡単に行えます。
まとめ

この記事では、DTM(デスクトップ・ミュージック)とは、パソコンを使って音楽を制作すること、そして曲作りに楽器の経験や専門知識は必ずしも必要ではないことをお伝えしてきました。
楽譜が読めなくても、楽器が弾けなくても、あなたの頭の中にあるメロディや、ふとした瞬間に思いついたアイデアを「曲」というカタチにできるのがDTMです。マウスで音を一つひとつ並べていく地道な作業も、それがメロディとして再生された瞬間の感動は格別です。
曲作りの中心となるのは「DAW」と呼ばれる総合音楽制作ソフトです。まずはこのDAWソフトがあれば、ほとんどの音楽制作を始めることができます。
「自分にできるだろうか」と不安に思うかもしれませんが、大切なのは専門知識よりも「こんな曲を作ってみたい」という好奇心です。
次は、「あなたにピッタリのDAWの選び方」についてご紹介しますので、そちらもぜひ参考にしてみてくださいね。







