Bluetooth 対応機器で何ができる?
まずはBluetooth対応機器を使ってどんなことができるのか?代表的な例を挙げてみましょう。「NFC」に関しては後述します。
- ヘッドホン(イヤホン)+スマホ
- バッグにスマホを入れたまま通話や音楽リスニング
- パソコン+マウス&キーボード
- ワイヤレスで操作
- スマホ&携帯プレーヤー+スピーカー
- ワイヤレスで音楽リスニング
- キーボード+シンセ
- ワイヤレスでシンセを演奏
- カーナビ+スマホ
- ハンズフリー会話
- 音楽リスニング
- 渋滞情報を知る
他にもBluetooth対応の機器には以下のようなものがあります
- ゲーム機・リモコン
- デジカメ・ビデオ
- 体重計・血圧計
このように対応機種やできることは多種多様ですが、これは今後もさらに増えていくと思われます。
それではつづいてBluetoothとNFCの特徴と違いをご説明いたします。
Bluetoothとは?
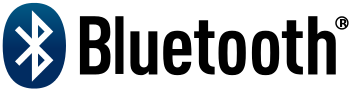
※Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG,Inc. が所有する登録商標です
Bluetoothは「2.4GHz帯の電波」という免許不用の電波帯域を使用した無線通信規格です。
特徴(後述のNFCと比較して)
- 通信速度が速い(最大24Mbps)
- 通信可能な距離が長い(1m~100m程度)
- 規格名は「IEEE 802.15.1」
インターネットに接続したり、比較的大きなサイズのデータを転送することもできます。なお、Bluetoothと無線LAN(2.4GHz帯)は同じ周波数帯を使っているため、Bluetooth機器を使用する際に無線LANの速度が低下する場合もあるようです。
※「Bluetooth=青い歯」という名前の由来はこちらを参照下さい。
ペアリング
Bluetoothで無線通信するためには、最初に互いを認証する作業(ペアリング)をおこなわなくてはなりません。たとえば満員電車の中でBluetooth対応イヤホンを使って音楽を聞く際に他人のBluetooth対応音楽プレーヤーと混線してしまったら大変ですね。そのため「一対一」の接続を行うためこのペアリングという作業が必要になるのです。
例)iPhone 6のBluetooth設定画面。下図ではIK MultimediaのiLoudと接続済

ペアリングの方法は機器によって異なりますが、取扱説明書等に方法が記載されています。初めて接続する機器同士の場合は最初に1回だけパスキー(PINコード)を入力する必要があります。2回目以降は自動で接続してくれるようになります。最近はほぼ半自動的にペアリングしてくれるモデルもあります。
機器間の相性によっては毎回パスキーを入れなくてはならない場合もありますが、いずれにせよペアリング作業は面倒だと感じる方も多いと思います。
到達距離は「class」で変わる
Bluetoothはどのくらいの距離まで届くのでしょうか?それは電波強度を規定した「class(クラス)」で決まります。対応機器がどのクラスかによって到達距離が異なるわけです。到達距離は遮蔽物等によって減少しますのであくまで目安と考えて下さい。なお異なるクラス同士の機器の接続も可能となっています。
| 出力 | 到達距離 | |
| class1 | 100mW | 約100m |
| class2 | 2.5mW | 約10m |
| class3 | 1mW | 約1m |
現在発売されているデバイスの多くはClass2といわれています。
※同じclassに分類されていても機種によって出力が大きく異なります。
※日本国内では電波法上、出力の上限が規制されています。
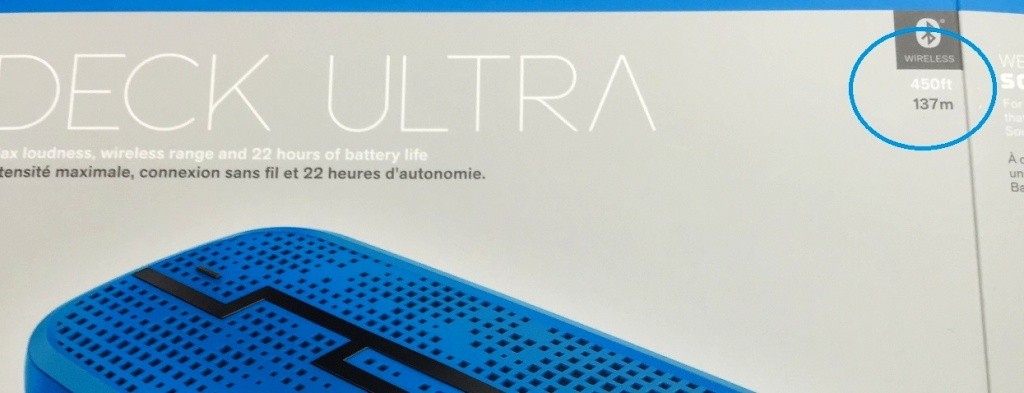
※137mとどくと謳っているSOL REPUBLIC 「DECK ULTRA」
Bluetoothのバージョン
Bluetoothには多くのバージョンがありますが、現在(2018/9月時点)では5が最新です。バージョン間の違いは主に通信速度や電力消費量といったものになります。
3.0では最大通信速度が24Mbpsまで拡張可能で、4.0では通信速度の向上に加え大幅な省電力化を実現する低消費電力モードBLE(Bluetooth Low Energy:Bluetooth LE)に対応しました。4.2では通信速度が4.0の2.5倍高速化されています。なおこのBLEを使ってワイヤレスでMIDIを送受信する規格は「MIDI over Bluetooth LE(Low Energy)=BLE-MIDI」といい、最近ではこのBLE-MIDIに対応したMIDIキーボードも発売されています。
たとえばBLE-MIDI対応のiPadで、音楽アプリ「Garageband」を立ち上げれば、ワイヤレスで打ち込みや演奏も行うことができるわけですね。
MIDI端子を装備した、シンセサイザー、電子ピアノ、電子ドラムなどに取り付けることで、iPhone / iPad / Macなどと楽器をワイヤレスでMIDI接続できるようにする、Bluetooth対応のアダプター「MD-BT01」「UD-BT01」といった製品もあります。
BLE規格を採用したブランド名「Bluetooth Smart」は、OS XやLinux、Windows 8、iOS、Android、Windows Phone、BlackBerryも対応しています。今後はBluetooth搭載のスマホの大部分がBluetooth Smartをサポートすると言われています。
プロファイル
Bluetoothにはさまざまな機能を持つ機器との接続を行うことができるので、機能ごとに通信ルールが決められています。これを「プロファイル」といいます。接続のためには機器同士が同じプロファイルに対応している必要があります。
プロファイルの例
- FTP(File Transfer Profile):パソコン同士でデータ転送をする
- HSP(Headset Profile):ヘッドセットと通信する
- HFP(Hands-Free Profile):ハンズフリー通話をする
- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile):ステレオ音声をレシーバー付きヘッドフォン(イヤホン)に伝送。
- GATT (Generic Attribute Profile):BLEで通信をする場合の基本プロファイル。他と組み合わせて使用される
- etc
【参考】
プロファイルの一覧はこちらを参照。
コーデック
Bluetooth機器同士で音声を伝送する場合は前述の「A2DP」プロファイルが必要となり、その際には音声を圧縮する必要が生じます。この圧縮方式(コーデック)には以下の様なものがあります。
- SBC
- A2DPの標準コーデック。遅延や音質劣化が欠点だが利用可能な製品が多い。
- AAC
- 主にiPhone、iPad等 高音質・低遅延
- apt-X(aptX):アプトエックス
- 主にAndroid端末 高音質・低遅延(48kHz/16bit)
- aptX HD
- aptXの拡張。ハイレゾ相当(48kHz/24bit)の高音質伝送が可能。
- HWA
- High-Res Wireless Audio ファーウエイ社が開発(96kHz/24bit)
- LDAC
- ソニーが開発。ハイレゾにも対応(96kHz/24bit)
一昔前はSBC(SubBand Codec)対応機種ばかりでしたが、音質の問題から現在ではapt-XやAACを採用した機器が多くなっています。
備考:aptX™ ローレイテンシー
Bluetooth® 対応のワイヤレス機器で、確実に映像と同期した音声を提供できるクアルコム・グローバルトレーディング社のコーデックテクノロジー。遅延を削減し、エンド・トゥ・エンドでオーディオ送信を改善するため、高品質で同期の取れたユーザー体験を実現する。
-
40ミリ秒未満のレイテンシーをサポート
-
48kHz / 16bit LPCM オーディオデータに対応
-
aptX™製品との下位互換性を維持
-
ワイヤレスによる音声と映像の同期問題を最小に抑制

「Bluetooth対応」であればなんでも良いというわけではない?
SBC以外のコーデック同士には互換性はないので、送信側と受信側が同じBluetoothコーデックに対応していないと高音質・低遅延の恩恵をうけることができません。たとえば送信側がAACのみ、受信側がapt-Xのみの場合はコーデックにはSBCが使われることになります。
なおここで注意しなくてはならないのは「音声ファイル自体のフォーマットとBluetoothの送信コーデックを混同しない」ということです。たとえば送・受信機器が下記のような組み合わせの場合はどうなるか考えてみてください
- 送信側:AACファイルを再生可能。Bluetooth送信コーデックSBCと apt-X
- 受信側:Bluetooth 対応コーデックSBCとAAC
少々ややこしい話ですが、AACが読めるから必ずしもBluetoothコーデックにAACが使えるわけではありません。したがってこの場合は音質の悪いSBCで送信されてしまうわけですね。
なお音楽ファイルがもともとAACで、かつBluetoothの送信コーデックがAACであれば送信時に再度圧縮することなくそのまま送信さえるので音質劣化がないといわれています。
送信側と受信側の対応コーデック(LDACを除く)の組み合わせと、実際に使用されるコーデック(黒文字)。
| 送信側/受信側対応 | SBC | SBC+apt-X | SBC+apt-X+AAC |
| SBC | SBC | SBC | SBC |
| SBC+apt-X | SBC | SBC | apt-X |
| SBC+AAC | SBC | AAC | AAC |
| SBC+apt-X+AAC | SBC | AAC | apt-X |
せっかく高価なスピーカーを買っても、プレーヤーとのコーデックの相性が悪いとそのパフォーマンスを十分に活かすことができなくなる場合もあるということですね。
以上機材選びの際の参考にしていただければ幸いです。

NFCとは?

NマークはNFC Forum, Inc. の米国およびその他の国における商標または登録商標です
次は最近スマホなどでもよく見かける「NFC」ですが、NFCとは「Near Field Communication」の略で、国際標準規格の近距離無線通信技術です。Wi-FiやBluetooth同様に無線通信ができますが、10cm程度の非常に近距離感での無線通信を行う規格です。
特徴(Bluetoothと比較して)
- 通信速度が遅い(最大424kbps)※(424キロビット/秒)
- 通信可能な距離が短い(~1m程度)
- ワンタッチで機器認証ができる。
NFCは通信速度が遅いため、相互接続して直接音楽データをやり取りするのには向いていません。NFCの一番の利点はワンタッチで機器認証と通信ができることです。
ハンドオーバー
たとえばBluetooth機器同士を接続する際のペアリング作業をNFCで行うことで、お互いをかざすだけでペアリング完了、あとはBluetoothで音を飛ばす。といったことができるようになるのです。つまりパスキーを入れる手間が省けるわけですね。
このようにペアリングと認証だけをNFCで行い、通信はWi-FiやBluetooth等の高速な規格に引き継ぐことを、ハンドオーバーと呼びます。特に複数の機器との接続、切断を行う場合などはこのハンドオーバーは超便利ですね。
将来的な可能性
ハンドオーバー以外にもNFC対応のヘッドホンやスピーカーの電源のON、OFFといったこともこのNFCで可能になります。
ほかにもNFC対応機器を使うことで、スピーカーの他にもNFC搭載の携帯電話をNFC対応テレビにかざすことで、携帯で撮影した写真をテレビで見たり、NFC対応プリンターで写真を印刷するといったことも可能となるわけです。
NFCはFeliCaやMIFAREといった非接触ICカードとは上位互換性を持っています。したがってNFC=FeliCaではないことに注意して下さい。
このようにNFC技術は、ハンドオーバーのような「認証」、FelicCaなどの「決済」といった目的で活用されていく傾向のようです。
NFCの通信規格を搭載している機器同士は双方向に通信可能なため、今後さまざまな分野での活用が期待されています。
対応スマホはこちら等のページでチェックできます。なおiPhone6はApple PayとしてNFC対応となったのですが国内での決済サービスは未定となっています。
★
というわけで Wi-Fi、bluetooth、NFC の違いはおわかりいただけましたでしょうか?この他にも遅延が少なく、障害物にも強く到達距離も長い「デジタルワイヤレス(2.4GHzデジタル方式)」といった方式を採用したヘッドホンもあります。
それぞれの長所や短所を理解してうまく使い分けていきましょう。
【あわせて読みたい記事】
ブルートゥース対応のスリムなMIDIキーボード CME Xkey Air を試してみた
ケーブルいらず!ワイヤレスでMIDI入力可能な KORG micro KEY 2 Air シリーズ 発表
YAMAHA ワイヤレス MIDI/USB MIDI インターフェース MD-BT01 UD-BT01発表
この記事を書いた人

デジランド・デジタル・アドバイザー 坂上 暢(サカウエ ミツル)
学生時代よりTV、ラジオ等のCM音楽制作に携り、音楽専門学校講師、キーボードマガジンやDTMマガジン等、音楽雑誌の連載記事の執筆、著作等を行う。
その後も企業Web音楽コンテンツ制作、音楽プロデュース、楽器メーカーのシンセ内蔵デモ曲(Roland JUNO-Di,JUNO-Gi,Sonic Cell,JUNO-STAGE 等々その他多数)、音色作成、デモンストレーション、セミナー等を手がける。











