KAWAIグランドピアノの魅力発見ノート 〜職人のこだわりと音の世界〜
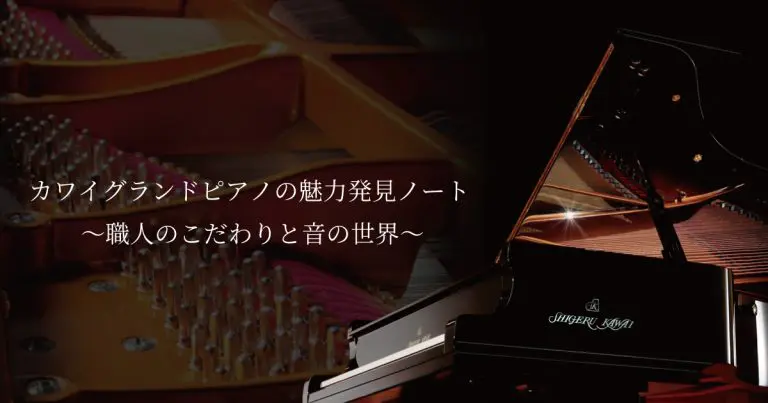
河合楽器のこだわりやヒストリー、グランドピアノの特徴、現行品番の仕様や解説などについては、すでに他に詳しいサイトが沢山あります。そこで、今回は私が自分用のノートに記録してきた「ピアノの仕事メモ」の断片的な内容からKAWAIのピアノの魅力をお伝えできたらと思います。このメモはKAWAIに関するもので、私が日々のご案内の中でお客様からいただいた言葉や、ピアノの先生や愛好家の方々のお話、読書、各種のインタビュー、公開講座、製品研修、調律師の方の言葉を記録してきたものです。文章は私個人の解釈が入っています。また、ファクトチェックはしていないことをご理解ください。KAWAIのピアノを弾く時、お客様とピアノの間をよりよくつなぎ、より楽しんでいただくきっかけの一つとなれば幸甚です。
1. 創業者と理念
創業者・河合小市
河合楽器製作所(KAWAI)の創業者・河合小市は、明治36年に山葉楽器製造所(現在のヤマハ)で日本初の純国産ピアノを完成させました。彼は、それまで輸入していたピアノアクションの国産化に成功し、その努力と才能によって日本のピアノ製作の礎を築きました。浜松という土地から、多くのものづくりの偉人が輩出される中、小市もまたその一人でした。
二代目・河合滋
河合小市の理念を受け継ぎ、二代目の河合滋は「世界一のピアノを目指すこと」を掲げました。彼はグランドピアノ専門の工場を設立し、その集大成としてShigeru Kawaiのブランドを生み出しました。現在では、KAWAIはショパン国際ピアノコンクールの公式ピアノの1つとして認定されるまでになりました。
2. ピアノづくりのこだわり
熟練の技と機械の融合
KAWAIのピアノは、最先端の技術と熟練の職人技が融合したものです。原器工程と呼ばれる「手作り工程」を大切にし、ノミやカンナを使って木と向き合う職人の育成を重視しています。また、組立や調整は必ず人の手で行い、その技術を次世代へ継承しています。
時間を惜しまないこだわり
理想的な音を実現するため、響板の天然乾燥にこだわり、モデルによっては5年~10年以上もの時間をかけることもあります。
徹底した研究と挑戦
KAWAIは、ピアニストの厳しい要求、現場の調律師や生産技士の声に応えながら研究を重ねています。伝統を重んじながらも、常識にとらわれず新たな挑戦を続ける姿勢は、創業者・河合小市と二代目・河合滋の精神を受け継いだものです。
人の手による仕上げ
どれほど機械化が進んだ工場であっても、KAWAIのピアノには職人の手のぬくもりが感じられます。出荷前には防音室で1人の調律師が最終調律を行い、ピアノ1台1台と向き合います。また、たとえば「弦を押さえて音を止めるダンパーのセッティング」ひとつをとっても、専門の技師が時間をかけて丁寧に仕上げています。
3. よいピアノとは
よいピアノの条件
- 表現力があること
- 弾き手の要望に反応すること
- 新しいインスピレーションや欲求を与えてくれること
表現力
ピアノの表現力は、音の強弱やタッチの微妙なニュアンスをどれだけ忠実に再現できるかにかかっています。
例えば、絵を描く時にさまざまな色を選び、タッチを工夫するように、ピアノでも異なる音を作り出すことが求められます。曲や時代によってペダリングを変えることも必要です。和声を直感的に感じたり、研究したりすることが大切になります。
4. 音の印象
KAWAIのピアノには、モネの絵のような柔らかく幻想的な音を奏でる個体もあれば、フェルメールの光と影を表現できるような個体もあります。
KAWAIの音の特徴
- 低音の響きが重厚で、オルガンサウンドのような深みがある。
- 音の立ち上がりが良く、自然な音の伸びと減衰が感じられる。
- 音の芯、輪郭、色合いがはっきりしていながら、独自の個性を持つ。
- 木の温もりを感じられる音で、ピアノが木でできていることを実感できる。
- 音の強弱、クリアさ、まろやかさを一台のピアノの中でバランスよく表現できる。
5. 鍵盤の印象
KAWAIの鍵盤は、程よい抵抗感がありながら軽やかでコントロールしやすい設計になっています。学生の頃は「KAWAIの鍵盤は重い」と感じていましたが、単なる軽さや弾きやすさではなく、弾き方によって音の出方が変わるため、研究しがいのある鍵盤だと気づきました。
また、適当に弾くと音もルーズになるため、練習中に気を抜くことができません。そのため、KAWAIの鍵盤は集中力を高めてくれると感じます。
6. ピアノと調律師
ピアノの状態は日々変化します。その要因は、気温や湿度の影響だけでなく、演奏者の体調やメンタルにも左右されることがあります。
調律師と相談しながら調整を加えてもらうことで、ピアノの音が変わる(良くなる)と実感することが多くあります。調律師は、ピアノと弾き手のイメージをつなぐ存在です。彼らは技術を高めるだけでなく、音楽に対する造詣の深さや感性、人間性も磨く必要があります。
発表会でKAWAIのピアノを弾く際には、調律師と先生が意見交換しながら調整を行い、最終的にホール、曲、弾き手が一体となるよう仕上げていくプロセスに感動しました。
7. 日本のものづくりと未来
1927年に創業したKAWAIは、もうすぐ100周年を迎えます。
これからも、日本のものづくりの精神を受け継ぎながら、世界中で愛されるピアノを作り続けてほしいと願います。
I hope you have an encounter with a good piano in the world of pianos.



